私たちの毎日は、電気とともに動いています。
目覚まし時計の音で一日が始まり、炊飯器がごはんを炊き、エアコンが部屋の空気を整えてくれる。
夜になれば照明が灯り、テレビやスマートフォンでくつろぐ時間が生まれる。
家庭だけでなく、店舗やビル、工場や病院。
あらゆる場所で当たり前のように使われている電気。
その“当たり前”を支えているのが、電気工事士の仕事です。
見えない場所で、電気が安全に流れる道をつくる。
機械が動き、明かりが灯り、人が安心して暮らせる環境を整える。
電気工事士は、暮らしや生活、そして社会全体を根底から支えているプロフェッショナルです。
この記事では、電気工事士の仕事内容をはじめ、関わる現場の種類や必要な資格、働き方のスタイルまでをわかりやすく紹介します。
また、仕事のやりがいや、未経験からでも目指せるキャリアの道のりについても触れていきます。
行橋市の暮らしを、半世紀以上そっと支えてきた林田電気工業だからこそ伝えたい。
電気工事士という仕事の魅力と、その先にある人と社会のつながりを、あなたにも知ってもらえたらと思います。

株式会社 林田電気工業
林田竜一
代表取締役
行橋市で電気工事会社を経営しています。お客様ひとりひとりに丁寧に対応し、電気でつなぐ明るい未来をスローガンに地域に貢献できるように努めています。
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
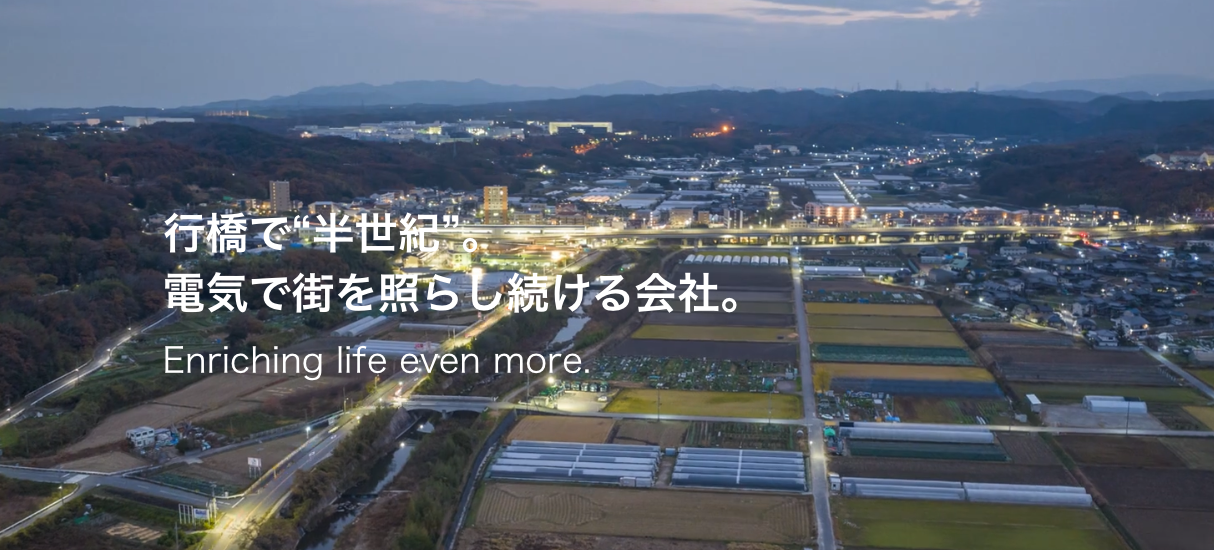
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
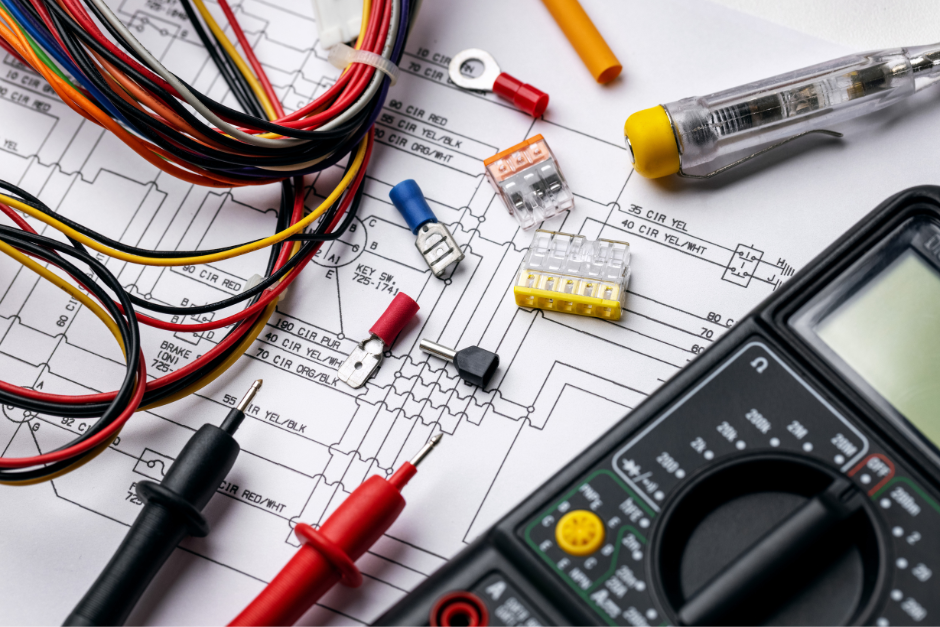
私たちが毎日あたりまえのように使っている電気。
照明がつく、家電が動く、スマートフォンが充電される。
でも、こうした「当たり前」は、誰かの手によって支えられていることをご存じでしょうか。
電気工事士は、建物や設備に電気を安全に届けるために、配線工事・点検・機器の設置などを行う専門職です。
この仕事は国家資格が必要であり、法的にも“有資格者だけができる工事”が定められています。
住宅やマンション、店舗やオフィス、工場やビル、さらには学校・病院・信号機・街灯まで。
電気工事士が携わる現場は、私たちの暮らしのあらゆる場面に広がっています。
新築時の配線、リフォームの電気設備の改修、省エネ対策やスマートホーム対応など、求められる技術も年々進化しています。
また近年では、再生可能エネルギーの導入やEV充電設備、さらには災害復旧など、電気工事士の活躍フィールドはますます広がっています。
災害時には、地域の停電復旧や仮設住宅の電気整備といった命を支える現場でも、彼らの技術が頼りにされています。
このセクションでは、電気工事士の基本的な仕事内容を通して、「この仕事が社会にどれだけ深く関わっているのか」をわかりやすくお伝えします。
“電気を通す”というシンプルな言葉の裏にある、責任とやりがいのある仕事の全体像を、ここでしっかりと知っていただけたらと思います。
電気工事士の仕事の役割とは?
私たちの暮らしに欠かせない「電気」。
電気工事士は、その電気を安全に、確実に届けるために欠かせない専門職です。
建物の中でスイッチを押せば灯りがつき、エアコンが動く……
そんな当たり前を裏で支えているのが電気工事士の仕事です。
電気工事士が担うのは、電気を流すための「配線の設計・施工」、それにともなう機器の「設置・点検・修理」。
新築の住宅から店舗、工場、公共施設まで、建物の種類や規模に応じたさまざまな現場で活躍します。
作業の対象となるのは、屋内だけでなく、電柱や変電設備などの屋外設備も含まれます。
さらに近年では、太陽光発電やEV(電気自動車)充電設備など、再生可能エネルギーや新技術にも対応する現場が増えています。
以下に、電気工事士の代表的な役割をまとめました。
| 役割カテゴリ | 内容の例 |
| 配線の設計と施工 | 電気の流れを考慮し、配線ルートを計画・施工する |
| 機器の設置と接続 | 照明、コンセント、分電盤、空調設備などを取り付ける |
| 点検・保守 | 定期的な安全確認や、異常時の修理対応を行う |
| 災害復旧 | 台風・地震などの災害時、停電復旧や仮設住宅の配線を担当 |
| 新技術への対応 | 太陽光、蓄電池、スマートホーム設備などの先進機器に対応する |
こうした業務の多くは国家資格を持つ電気工事士だけが法律上対応できる「独占業務」です。
つまり、社会にとって不可欠でありながら、簡単には代えのきかない職業でもあります。
電気工事士の仕事は、ただ配線をつなぐだけではありません。
人が安心して暮らすための「電気の道」をつくる、責任とやりがいのある仕事です。
私たちの暮らしと電気工事士の仕事のつながり
毎日の暮らしの中で、電気の存在を意識することはあまり多くないかもしれません。
けれど実際には、電気がなければ照明も冷暖房も動かず、スマートフォンの充電すらできなくなります。
その電気を「安全に」「確実に」届けてくれているのが、電気工事士の仕事です。
電気工事士の活躍の場は、家庭だけではありません。
コンビニや病院、オフィスや工場、さらには学校・駅・信号機などの公共インフラまで、生活と経済のあらゆる場面で必要とされています。
以下に、電気工事士が活躍している代表的な場所と役割をまとめました。
| 活躍する場所 | 具体的な工事内容 |
| 一般住宅・集合住宅 | 配線、照明、コンセント、分電盤、空調機器の設置など |
| 商業施設・オフィス | 店舗照明、空調制御、防犯カメラ、LAN配線、看板用電源の設置 |
| 工場・大型施設 | 動力設備、機械への電源供給、制御盤設置、非常用電源の整備 |
| 公共施設・インフラ | 街灯・信号機の電源、学校・病院の配線、災害時の仮設設備の整備など |
これらの現場では、「内線工事(建物内の工事)」と「外線工事(電柱や屋外設備の工事)」に分かれて作業が進みます。
内線工事は、照明やコンセントの設置といった身近な工事が中心。
一方、外線工事は高所作業を伴い、より大規模で専門的な知識と技術が求められます。
どの現場でも共通しているのは、電気工事士が“社会の安心と機能”を下支えしているということです。
表には見えなくても、電気が通るその裏側に、工事士の技術と想いが込められているのです。
AIでは代替できない電気工事士の現場仕事の価値
AIやロボットが進化して、多くの仕事が自動化されている今。
「この先、機械に仕事を奪われてしまうのでは」と感じる人も多いかもしれません。
そんな時代でも、電気工事士の仕事は今なお“人の手”が求められ続けています。
電気工事士の仕事には、現場での柔軟な判断力や、危険を見極める感覚が欠かせません。
同じ図面でも、建物の構造や周囲の環境によって、作業手順を調整する必要があるのです。
また、災害時や緊急時の復旧作業では、素早く正確に判断できる“経験”こそが命を守ります。
以下に、電気工事士がAIに代替されにくい理由をまとめました。
| ポイント | 内容 |
| 判断と対応力 | 図面通りにいかない現場で、柔軟に対応しながら安全を確保 |
| 現場ごとの状況変化 | 建物の構造、天候、人の動きなど、条件が毎回異なる |
| 技術の継承 | OJT(現場教育)で人から人へ伝える職人気質のある世界 |
| 緊急・災害対応 | 被災地や停電現場では、人の判断と迅速な作業が何よりも必要とされる |
例えば、突然の停電が起きたとき。
システムが自動で原因を診断するのではなく、電気工事士が現場に駆けつけ、状況を見て対応します。
このような「その場での判断」が必要な仕事は、AIにはまだ難しい領域です。
経験を積みながら技術を磨き、一人前になれば年齢を問わず長く活躍できます。
現場で汗をかき、仲間と支え合いながら人の役に立つ……
そんな電気工事士の仕事には、これからの時代にも必要とされる確かな価値があります。
それでは、電気工事士の仕事は分野別にどんなふうに分けられるのでしょうか。
「電気工事」と聞くと、家庭の照明やコンセントを思い浮かべる方も多いかもしれません。
でも実は、電気工事士の仕事はもっと広く、深く、社会のあらゆる場面に関わっています。
住宅の新築やリフォームでの配線工事。
店舗やオフィスでの照明・空調・通信設備の整備。
工場や病院では、大型設備の電源や制御システムを扱う高度な工事も行われます。
さらに、学校や役所、信号や街灯といったインフラも電気工事士の手で支えられています。
そして災害が起きたとき……
停電の復旧や仮設住宅への配線、避難所の電源確保など、人の命と希望をつなぐために、最初に“灯り”を取り戻す仕事を担うのが、電気工事士です。
電気があることで、暮らしが動き出します。
その根っこを支えるプロフェッショナルとして、電気工事士の役割はこれからますます広がっていきます。
次は、それぞれの現場でどんな仕事があるのか、分野ごとに見ていきましょう。
住宅を支える電気工事士の仕事
住宅の電気工事は、日々の生活を支える基盤となる重要な仕事です。
電気工事士は新築やリフォームの現場で、安全かつ快適に電気が使えるよう配線を整え、照明やコンセント、分電盤を設置します。
特に家庭では、暮らし方に応じた柔軟な設計と丁寧な施工が求められます。
| 工事項目 | 主な内容 |
| 配線工事 | 電線を壁や天井に通して電気を届ける |
| 照明・コンセント設置 | 照明器具や電源の配置と接続 |
| 分電盤設置 | 回路ごとに電気を分ける制御装置の設置 |
| 内線工事 | 建物内で行う配線や機器の取り付け |
たとえば、リビングの照明やエアコン、キッチンの電子レンジ、洗濯機など、多くの家電製品を安全に使えるようにするためには、計画的な配線と分電盤の設定が必要です。
また、コンセントの数や位置は、将来の暮らし方まで見据えて決めることもあります。
最近では、スマートスピーカーと連動する照明システムや、IoT対応のエアコンなどを導入する家庭も増えています。
電気工事士はこうしたスマートホーム設備にも対応し、ネットワーク機器やセンサーと連携した配線も行います。
さらに、太陽光パネルやEV(電気自動車)用充電器の設置といった、省エネ・再生可能エネルギーへの対応も進んでいます。
これらの設備は通常の家庭電源とは異なる知識と技術が求められるため、電気工事士の役割はますます広がっています。
住宅という最も身近な空間に、電気工事士は安全と快適を届けるプロフェッショナルとして関わっています。
日頃の生活を支える、その“当たり前”をつくっているのが、住宅を支える電気工事士の確かな仕事なのです。
店舗やオフィスを支える電気工事士の仕事
商業施設やオフィスの電気工事は、業務の「止まらない」環境づくりが大前提です。
多くの人が働いたり訪れたりする場所では、快適さや安全性、効率性がすべて電気設備に関係しています。
だからこそ、電気工事士はスピード感と正確さを求められます。
| 項目 | 内容 |
| 照明設備 | 明るさ・演出を支える工事 |
| 空調設備 | 冷暖房・換気システムの電源 |
| 通信・防犯設備 | ネット・監視機器の設置 |
| 非常用電源 | 災害時も機能する予備電源 |
例えば、店舗では照明の配置や色温度が、来店者の印象や滞在時間に影響します。
オフィスでは、空調や照明のバランスが仕事の集中力に直結するため、工事士の配慮が不可欠です。
防犯設備や通信機器の設置も、営業中のトラブル回避やネットワーク環境の安定に貢献します。
近年では、BCP(事業継続計画)に対応した非常用電源の設置も増えており、災害対策としての工事も重要な役割です。
このように、商業や業務の現場では「止めない・途切れさせない」電気環境の整備が求められます。
万が一の災害時にも業務が止まらないようにするため、あらかじめ備える役割を電気工事士が担っています。
商業施設や店舗、オフィスの電気は、快適さ・安全性・業務効率を支える基盤です。
その環境をかげで守っているのが、電気工事士の確かな技術と判断力なのです。
工場・大型施設を支える電気工事士の仕事
工場や大型施設で活躍する電気工事士は、設備全体の「動力」と「安全」を支える役割を担っています。
日々多くの人が働き、多くの機械が動く現場では、安定した電力供給と精密な制御が欠かせません。
そのため、高度な専門性と正確な施工が求められます。
以下に、主な仕事内容を分かりやすく整理しました。
| 分野 | 主な役割 |
| 動力設備 | 工場の機械に電気を送る |
| 制御盤 | 生産ラインの自動制御 |
| 非常用電源 | 停電時に機能を維持する電力を確保 |
| 高圧受電設備 | 施設全体に高圧電力を供給 |
たとえば、動力設備は、製造機械や搬送装置などに電気を届けるための大型配線やブレーカー設置を含みます。
制御盤は、ライン上の各装置を連携させる「頭脳」のような存在で、自動で動く機械の流れを管理します。
非常用電源は、病院や物流倉庫などの大規模施設で、災害時にも止まらない電力を供給するために設置されます。
高圧受電設備は、電力会社から供給される高圧電力を建物内で使える電圧に変換し、各設備に安定して送ります。
これらの業務では、第一種電気工事士などの上位資格が必要な場面も多く、知識と技術の両方が求められます。
その分、スキルアップが目に見えやすく、キャリア形成にもつながる分野です。
大きな現場を支える電気工事士の仕事は、社会を動かす力そのものといえるでしょう。
公共施設やインフラを支える電気工事士の仕事
学校や病院、役所、信号機、街灯など、私たちの生活を支える「公共インフラ」。
これらはすべて電気の力で動いています。
もし突然、電気が使えなくなったら――医療現場は停止し、街は混乱し、日常の安全は簡単に崩れてしまいます。
そんな事態を防ぐために、電気工事士は社会のあらゆる場所で働いています。
見えないところで地域の安心を守る、それが彼らの仕事です。
以下に、公共施設・インフラ分野での主な仕事内容をまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 対象施設 | 学校、病院、役所、信号機、街灯など |
| 主な作業 | 電気設備の設置、点検、修理、更新 |
| 特徴 | 高い公共性、安全性が求められる |
| 最近の傾向 | 災害対策やBCP(事業継続計画)対応、スマート信号機導入など |
たとえば、信号機の制御システムは交通事故を防ぐ要です。
病院の非常用電源は、命を救う医療機器を止めないために欠かせません。
街灯のLED化は省エネ効果だけでなく、夜の安全を守る手段でもあります。
また近年では、災害時の電力確保として非常用発電機や蓄電池の設置も重要な役割になっています。
鉄道や駅の照明・案内表示なども、電気工事士が関わるインフラの一部です。
公共施設やインフラの電気は、私たちの暮らしに安心と秩序をもたらします。
街灯が夜道を照らし、信号機が交通を整え、病院や学校では電気が命と学びを守っています。
そのすべてを止めないよう支えているのが、電気工事士の確かな技術と責任ある仕事です。
私たちが「当たり前」に過ごせる日常は、見えないところで働く彼らによって成り立っています。
公共の仕組みを影から支える存在として、電気工事士はこれからも社会の心強い要となるでしょう。
街を守る、災害復旧・復興で活躍する電気工事士
地震や台風などの災害が発生すると、まず必要とされるのが「電気の復旧」です。
照明、通信、医療、炊き出し。どれも電気がなければ成り立ちません。
その中で、被災地に最初の灯りを戻す役割を担うのが電気工事士です。
まさに、人の命と希望をつなぐ大切な仕事といえるでしょう。
以下に、災害時における主な対応内容を整理しました。
| 項目 | 内容 |
| 主な対応現場 | 停電地域、避難所、仮設住宅、公共施設など |
| 主な作業内容 | 電力の復旧、仮設配線、非常用発電機の設置 |
| 特徴 | 緊急性が高く、迅速な対応と柔軟な判断が求められる |
| 連携先 | 自治体、電力会社、消防・警察、地元企業など |
たとえば避難所では、仮設の照明や充電用電源を引くことで、夜間の安心や情報の確保が可能になります。
仮設住宅に配線を通す作業は、被災者が少しでも早く落ち着いた生活を取り戻すための第一歩です。
また、非常用発電機の設置によって、医療機器や通信機器が止まるのを防ぎ、命をつなぐ備えにもなります。
こうした現場は一刻を争う状況が多いため、日頃からの訓練や関係機関との連携が不可欠です。
電気工事士は、災害時にすぐに動けるよう準備を整え、社会を支える一員としての責任を果たしています。
災害時の電気は、安心と希望を取り戻すための最初のインフラです。
そして電気工事士は、電気を通してこの街の暮らしを静かに支え続けているのです。

「手に職をつけたい」
「電気に関わる仕事をしてみたい」
「人々の暮らしを支えるような仕事がしたい」
そんな気持ちを持つ人にとって、電気工事士という道は、現実的で頼もしい選択肢です。
電気工事士の資格は経済産業省が管轄する国家資格であり、学歴や経験を問わず、誰でも挑戦できます。
まず目指すのは、家庭や店舗などの身近な電気工事を担う「第二種電気工事士」
照明の設置やコンセントの増設、配線工事など、暮らしのすぐそばで役立つ作業が中心です。
試験は筆記と実技の2段階ですが、初心者向けの教材や講座も充実しています。
合格すれば、全国どこでも通用する国家資格保有者として、実際の現場で第一歩を踏み出せます。
そこから先は、より大きな施設や高圧設備を扱える「第一種電気工事士」へと進む道もあります。
第一種電気工事士は実務経験を積みながら段階的に取得を目指せます。
施工管理や独立開業など、さらに広いキャリアの可能性が開かれていきます。
何も知らなかった自分が、誰かの暮らしを守る技術者になっている……
そんな確かな成長と誇りを感じられることも、電気工事士の仕事の魅力です。
まず目指すのは第二種電気工事士|初心者でも取得しやすい国家資格
電気の仕事に関わる上で、最初に目指したいのが「第二種電気工事士」です。
「第二種電気工事士」の資格は、年齢・学歴・経験を問わず誰でも受験できる国家資格です。
家庭や小規模な店舗の電気設備を扱うため、生活に密着した現場で活躍できます。
手に職をつけたい人や、人々の暮らしを支える仕事に関心のある人にとって、最初のステップとしてぴったりの資格です。
以下に、第二種電気工事士の基本情報を簡単にまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 工事対象 | 一般住宅・小規模店舗(600V以下) |
| 主な作業 | 照明・配線・コンセント・エアコン・分電盤の設置 |
| 試験形式 | 学科(CBT)+技能(工具を使った実技) |
| 合格率 | 学科:約60% 技能:約70% |
| 受験資格 | 年齢・学歴・経験すべて不問 |
この資格で扱えるのは、たとえば住宅のリフォームで新しい照明をつけたり、コンセントを増設したりする工事です。
エアコンの専用回路工事や、電気を部屋ごとに振り分ける分電盤の取り付けも対象になります。
こうした作業は、快適な暮らしを支えるうえで欠かせないものです。
試験は、パソコンを使ったCBT(Computer-Based Testing)方式の学科試験と、実際に配線作業を行う技能試験の2段階です。
合格率も比較的高めで、初心者にも挑戦しやすいのが特徴です。
合格すればすぐに実務に就けるため、就職や転職の大きな後押しにもなります。
「電気に関わる仕事をしたい」「人の役に立つ技術を身につけたい」と考えるなら、第二種電気工事士から始めてみませんか。
第一種電気工事士とは?できる仕事と必要な実務経験
電気工事の現場でより大きな仕事を任されたい。
そんな思いを持つ人が次に目指して欲しいのが「第一種電気工事士」です。
「第一種電気工事士」の資格を持つことで、工場やビル、病院など、大規模な施設での工事が可能になります。
高圧電力(600V超)を扱うため、より高度な知識と技術が求められる資格です。
以下に、第一種電気工事士の基本情報を簡単にまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 工事対象 | 工場・ビル・病院などの大規模施設。600V超の高圧設備を含む工事。 |
| 主な作業 | 動力設備の電源工事、制御盤の設置や配線、保守・点検など。 |
| 試験形式 | 学科試験(マークシート)+技能試験(工具を使った実技)。 |
| 合格率 | 学科:約55% 技能:約65%(年度により変動あり)。 |
| 受験資格 | 誰でも受験可能。※免状の交付には実務経験が3年以上必要。 |
たとえば、工場では大型機械を動かすための電源工事や、設備全体の制御を担う制御盤の配線作業が重要です。
こうした作業には、安全性と正確さが欠かせません。
また、第一種電気工事士の資格があると、現場のリーダーや施工管理としても活躍できるほか、将来的な独立開業の道も開けます。
ただし、資格取得後すぐに働けるわけではなく、免状の交付には3年以上の実務経験が必要です。
また、取得後は5年ごとに定期講習を受ける必要もあります。
「第一種電気工事士」の資格は、専門性の高い仕事を通じて、長く安定したキャリアを築いていける大きな力になります。
第二種と第一種の違いを比較|キャリアステップとしての道筋
電気工事士の資格には、第二種電気工事と第一種電気工事という2つの国家資格があります。
どちらも電気工事を行ううえで必要な資格ですが、対応できる工事の範囲や求められる実務経験に違いがあります。
まずは、主な違いを簡単に見てみましょう。
| 比較項目 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |
| 工事範囲 | 一般住宅・小規模店舗(600V以下) | 工場・ビル・病院など大規模施設(600V超含む) |
| 実務経験 | 不要 | 3年以上必要(免状取得時点) |
| 定期講習 | 不要 | 5年ごとに必要 |
| 難易度 | やや易しい | やや難しい |
たとえば、第二種電気工事は家庭や店舗の配線・照明・コンセント工事など、身近な設備に対応します。
一方、第一種電気工事はビルや工場での高圧設備や大規模な動力機器の工事にも対応できます。
第一種電気工事の試験は、年齢や学歴に関係なく誰でも受験可能です。
ただし、試験に合格しても、3年以上の実務経験がなければ免状(資格証)を取得できません。
そのため、未経験の方にはまず第二種電気工事を取得し、実務経験を積んでから第一種へと進むステップが現実的です。
このように、電気工事士としての道は「第二種電気工事 → 現場経験 → 第一種電気工事」という流れが基本です。
段階的にスキルアップできるため、自信を持って仕事の幅を広げられます。
もちろん、「将来的に大規模な施設を担当したい」「独立も視野に入れている」といった人は、早めに第一種電気工事を目指してもよいでしょう。
自分の今の立ち位置と将来の目標に合わせて、計画的に進むことが大切です。
それぞれの資格には、暮らしや社会を支える確かな価値があります。
電気工事士の資格取得を支援する制度や環境
電気工事士を目指したいけれど、「学ぶお金や時間が不安……」という声は少なくありません。
電気工事士の資格取得に向けた支援制度は思った以上に充実しています。
未経験からでも安心してスタートできる環境が整っているのです。
| 支援の種類 | 内容の概要 | 官公庁・公式ソース例 |
| 企業の支援制度 | 企業による受験費用・講習費用の補助、合格手当の支給など(企業ごとに異なる) | ※各企業の就業規則・福利厚生規定 |
| 公共の学習機関 | 職業訓練校やハローワークでの講座提供。低料金または無料で受講でき、第二種・第一種電気工事士の受験も可能 | 【厚生労働省 】ハローワーク職業訓練 |
| 国の助成金制度 | 「人材開発支援助成金」など。企業が講習費や訓練中の賃金を一部補助。第二種電気工事士研修では受講料・賃金補助あり | 【厚生労働省】 人材開発支援助成金 |
| 教育訓練給付制度 | 雇用保険加入者が指定講座を受講し修了した場合、受講費用の20%(上限10万円)がハローワークから支給 | 【厚生労働省教育訓練給付制度 |
| 高校生向け補助 | 都立工業系高校生対象、資格取得費用の最大半額補助(東京都独自) | 【東京都教育委員会 】工科高校資格取得アシスト制度 |
| 試験制度の改善 | 2025年から第二種電気工事士の学科試験免除期間が「1年間」に延長(法改正による) | 【経済産業省】 電気工事士法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました |
たとえば、企業に勤めながら受験費用の補助を受けたり、合格すれば手当が出たりする職場もあります。
また、ハローワークや職業訓練校(就職に向けた技能を学べる公的施設)では、無料または低料金で学べる講座もあります。
さらに、「人材開発支援助成金」などの制度を使えば、企業が講習費を支援したり、訓練中の給与を一部補助してくれることも。
働きながらでも学びやすい環境が広がっています。
2025年からは、学科試験の免除期間も1年間に延長され、再チャレンジもしやすくなりました。
これから資格を目指す方にとって、始めるハードルは確実に下がってきています。
環境が整っている今が、スタートにちょうどいいタイミングかもしれません。

電気工事士の仕事は、活躍する現場や働き方によって、大きくスタイルが変わります。
たとえば、地域密着型の「町の電気屋」として、人の暮らしに寄り添いながら働く道もあれば、商業施設や大型ビルなどでスケールの大きな現場に関わることもできます。
最初は電気工事会社に就職し、さまざまな現場を経験しながら、自分に合った道を見つけていくことも十分可能です。
家庭や店舗の施工では、照明や空調といった生活に身近な設備を扱います。
公共設備やインフラ整備に携わる仕事では、災害時の復旧や避難所への電源工事など、社会を支える役割も果たします。
出張や高所作業が必要な現場では体力が求められる一方で、専門性や報酬面でのやりがいも大きく、若いうちから経験を積むには適した環境です。
電気工事士の資格と技術は、将来的に独立開業を目指すこともできる「手に職」です。
どの現場でも経験を重ねるほど、自分の得意や興味が見えてきます。
最初から完璧なキャリアプランを立てなくても、働きながら模索し、道を広げていける……それがこの仕事の大きな魅力です。
では、電気工事士には具体的にどんな働き方や仕事スタイルがあるのでしょうか。
次に、それぞれの現場での特徴や向いているタイプを見ていきましょう。
地域の暮らしを守る|“町の電気屋”として働くという選択肢
「地元で腰を据えて働きたい」
そんな人にとって、“町の電気屋”は現実的でやりがいのある選択肢です。
個人経営や小規模の電気工事店では、地域の住宅や施設の電気設備を直接支える仕事が中心となります。
小さな修理から、照明やコンセントの設置、省エネ機器の導入まで。
住民との距離が近く、頼りにされる実感を得やすいのが特徴です。
以下は、地域密着型の働き方に関する主な特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 主な仕事 | 住宅の修理、照明・分電盤の設置、省エネ機器の施工など |
| 顧客との関係 | 直接対応が基本。信頼関係がリピートや紹介につながる |
| 働き方の特徴 | 一人で対応することが多く、柔軟な判断と対応力が必要 |
| やりがい | 「ありがとう」が日常的にもらえる。地域に貢献できる |
| 向いている人 | 地元で働きたい人、人と話すのが好きな人、将来独立したい人 |
たとえば高齢の方から「蛍光灯をLEDに変えてほしい」と頼まれるような場面。
その場で対応できれば、「また何かあったらお願いね」と言ってもらえることも。
こうした信頼の積み重ねが仕事のやりがいにつながっていきます。
緊急対応や休日の出動が必要な場面もありますが、その分、地域とのつながりが強くなるという一面もあります。
電気工事士としての第一歩を踏み出す場所としても、“町の電気屋”は大きな可能性を秘めています。
家庭や店舗を支える|快適な暮らしをつくる施工の現場
照明がつく。エアコンが動く。コンセントが使える。
そんな「当たり前の快適さ」を支えているのが、家庭や店舗を対象とした電気工事の仕事です。
電気工事士として現場に立つことは、家づくりに直接関わることでもあります。
設計士や大工、他の職人と協力しながら、暮らしをかたちにしていく実感が得られるのが、この仕事の大きな魅力です。
完成後には自分の手がけた配線や設備が目に見える形で残るため、達成感も感じやすい環境です。
以下に、この働き方の特徴をまとめました。
| 主な対象 | 一般住宅、店舗、事務所など |
| 主な作業内容 | 照明、空調、コンセント、配線、防犯設備の施工 |
| 関わる相手 | ハウスメーカー、リフォーム業者、施主など |
| 求められる力 | チームワーク、段取り力、現場での対応力 |
| 技術トレンド | スマートホーム、IoT対応、ITツールの活用 |
| 将来の選択肢 | 独立開業、協力業者としてのフリーランス |
作業の中心は、照明・空調・防犯カメラなど、生活に直結した設備の施工です。
近年はスマートホーム対応の工事や、省エネ設備へのニーズも高まっており、技術の幅も広がっています。
また、IT化が進む現場では、施工管理アプリやタブレットを使って効率化を図るケースも増えています。
この分野は、将来独立を目指す人にとっても現実的な道です。
比較的小規模な工事が多く、設備や資材も個人で用意しやすいため、早い段階で経験を積めば、自分の裁量で働くことも可能になります。
暮らしをつくり、人に役立つ。そんな手応えを感じられるのが、この仕事の醍醐味です。
街を支える|公共設備やインフラ整備に携わる仕事
街のあちこちにある照明や信号、学校や病院などの公共施設。
こうした設備を安全に保ち、電気を途切れさせないよう整えるのも、電気工事士の大切な役割です。
インフラを支える現場では、確かな技術と同時に、社会全体を守る責任感も求められます。
この分野の大きな魅力の一つが「安定性」です。
多くの仕事は自治体やインフラ関連企業からの発注で、長期的かつ計画的に進められる傾向があります。
また、設備の老朽化や災害対応といったニーズが常に存在し、景気に左右されにくい点も特長です。
最近では働き方改革の影響もあり、夜間や休日作業の負担軽減など、環境面の改善も進んでいます。
以下は、この分野での働き方の主な特徴をまとめた表です。
| 項目 | 内容 |
| 主な現場 | 学校、病院、信号、街灯、道路、避難所など |
| 主な業務 | 設備の新設・更新、点検、災害時の復旧作業、防災無線や非常用電源の確保 |
| 安定性の理由 | 公共発注による長期案件、老朽化設備の更新需要、災害対応の必要性、社会的意義の高いインフラ整備 |
| 働きやすさ | 労働環境の整備が進みつつあり、夜間・休日作業の軽減や安全管理の強化が図られている |
| 向いている人 | 社会貢献にやりがいを感じる人、安定した仕事に就きたい人、災害時の復旧作業に関心がある人 |
たとえば、信号設備の交換工事では、数日かけて計画的に作業を進める一方、災害時には仮設住宅への配線工事など迅速な対応が求められる場面もあります。
どちらのケースでも、電気工事士の存在が地域の安全と安心を支えていることに変わりはありません。
社会の基盤に関わる仕事だからこそ、安定性とやりがいの両方を感じられるのが、この働き方の魅力です。
スケールの大きな現場に挑む|大型工事・出張案件という選択肢
大型の商業施設やビル、工場などの建設現場では、多くの人が関わるダイナミックな仕事が進んでいます。こうした現場での電気工事は、いわゆる「ゼネコン(総合建設業者)」が取りまとめるプロジェクトの一部として行われます。電気工事士は、その中で設備工事の担当者として関わります。
現場のスケールが大きい分、扱う電力や設備も大規模になります。高所作業や夜間作業も発生しますが、その分だけ報酬や手当が見込めるのも特徴です。体力や現場対応力が必要ですが、多くの職人や業者との連携の中で「段取り力」「応用力」など、実践的な力がぐんぐん身につきます。
若いうちからこうした現場に挑むことで、実務経験や技術力を早く積み上げることができ、将来のキャリアにもつながります。
| 働き方の特徴 | 内容 |
| 現場の種類 | 商業施設、工場、大規模ビルなど |
| 関わる企業 | ゼネコン(総合建設業者)案件が中心 |
| 求められる力 | 体力、高所対応、夜間対応、段取り力 |
| 得られる経験 | 大規模プロジェクトでの実務経験、現場力 |
| メリット | 高収入、スキルアップ、将来の選択肢が広がる |
たとえば、商業施設の照明設備やビルの電源供給ラインの設置、空調システムへの配線工事などが主な作業になります。ICT機器や監視カメラなど、先進設備への対応も含まれることがあります。
「現場は大変そうだけど、経験を積みたい」「技術を活かして大きな仕事がしたい」と思う人には、やりがいの大きい選択肢といえるでしょう。

電気工事士の仕事は、社会の当たり前を支える大切な仕事です。
照明や空調、信号、街灯の設置から、災害時の電力復旧まで、暮らしのあらゆる場面に関わります。
特に災害後には、避難所の電源確保や仮設住宅の配線工事など、復興の最前線で力を発揮します。
仕事内容は幅広く、住宅・店舗の配線から、工場設備のメンテナンス、大規模な公共工事までさまざまです。
AI(人工知能)では代替できない、現場での判断と技術が求められます。
自分の手で設備を整え、人の役に立つ実感が得られる。そんな仕事です。
この道は、学歴がなくても始められます。
資格は必要ですが、努力を重ねることで未来を切り開けます。
未経験からでも、現場で経験を積みながらスキルを磨くことができます。
林田電気工業では、働きながら学べる環境が整っています。
資格取得の支援や、実務を通じたOJT(現場での研修)で、一歩ずつ確実に成長できます。
「手に職をつけて、自分の力で生きていきたい」
そう思ったなら、今がその一歩目です。
林田電気工業の現場で、あなたの未来を築いてみませんか?
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
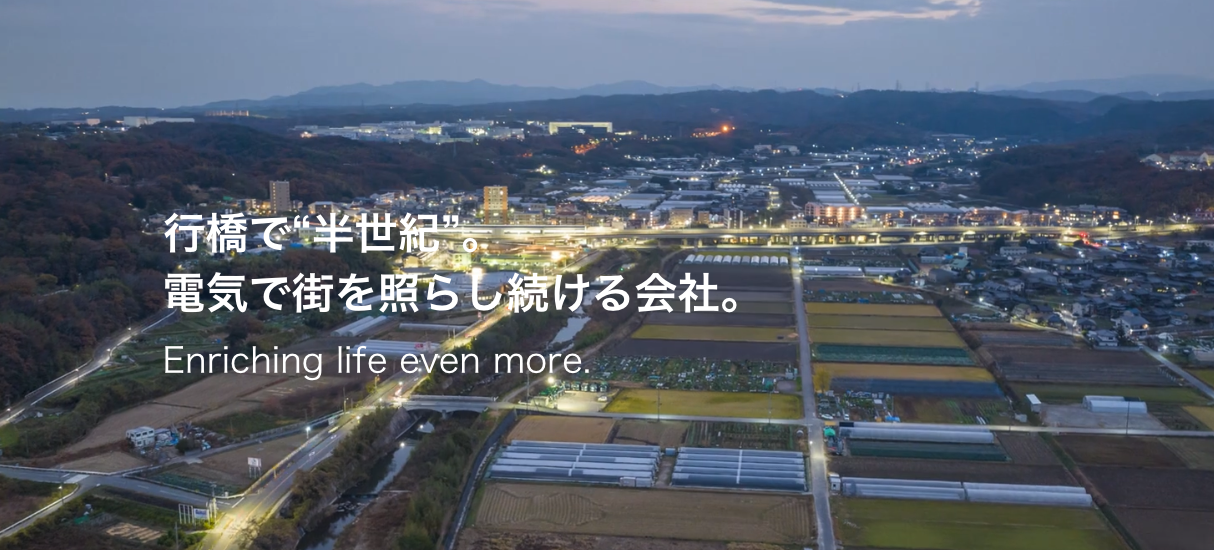
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
 電気工事メディア
電気工事メディア

