分電盤は、店舗の営業を支える電気設備の要です。
照明、エアコン、冷蔵庫、調理機器など、日常業務に欠かせない機器がトラブルなく動くのは、電気を安全に分けて届けるこの装置のおかげです。
ところが、設備の増設や年数の経過とともに、容量不足や劣化といった問題が静かに進行していることがあります。
「ブレーカーが落ちやすくなった」
「電気工事業者に分電盤の交換を勧められた」
そんなときは、今の設備が店舗の現状に合っていないサインかもしれません。
費用はいくらかかるのか。
工事はどのように進むのか。
営業を止めずに対応できるのか。
見直しを検討するうえで、知っておきたいことは少なくありません。
後回しにされがちなのが電気設備の整備です。
「まだ動いているから大丈夫」と思っていても、ある日突然ブレーカーが落ちて営業に支障が出る……そんなリスクは誰にでも起こりえます。
分電盤や電気容量は、正しく整えることで、店舗運営を止めないどころか、より安全で効率的な環境を支えてくれる強い味方になります。
この記事が、そうした安心を手に入れるための第一歩となり、自分のお店にとって必要な対策を考えるきっかけになれば嬉しいです。

株式会社 林田電気工業
林田竜一
代表取締役
行橋市で電気工事会社を経営しています。お客様ひとりひとりに丁寧に対応し、電気でつなぐ明るい未来をスローガンに地域に貢献できるように努めています。
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
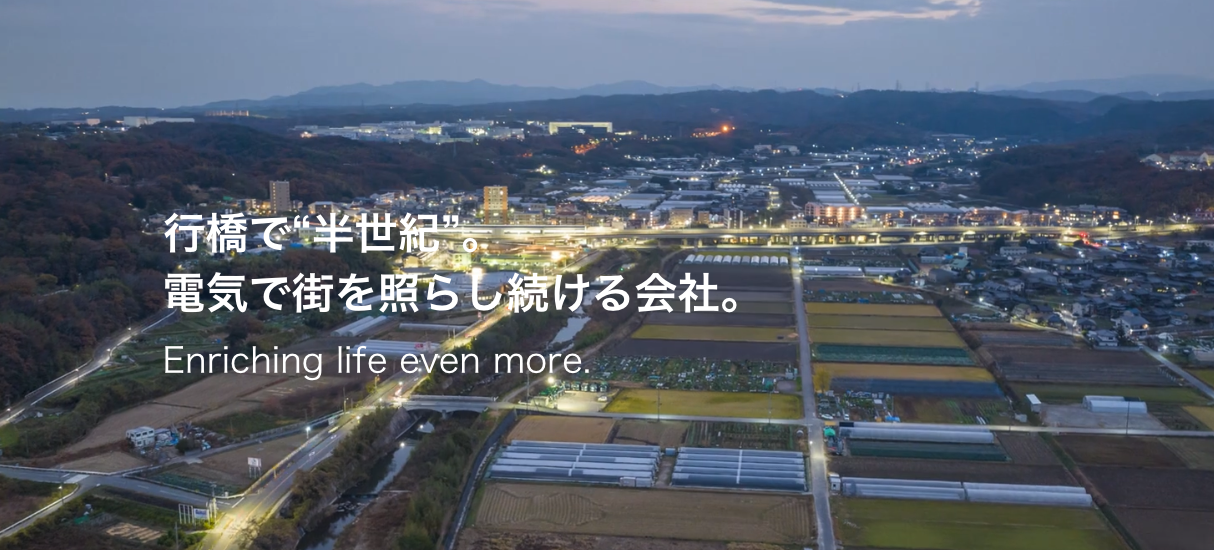
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

店舗で使われている照明や冷蔵庫、厨房機器など。
どれも電気が安定して供給されているからこそ、当たり前のように動いています。
電気の流れを裏側で仕切っているのが「分電盤」です。
目立たない場所にあっても、店舗の営業を静かに支えている重要な設備のひとつです。
ただ、設備が増えたり年数が経ったりすると、電気の流れが合わなくなることがあります。
ブレーカーが落ちやすい、機器が同時に使えない。
そんな不具合は、電気の容量や分電盤の設計が今の店舗に合っていないサインかもしれません。
分電盤の設計は店舗の業種によって大きく違います。
たとえば飲食店なら厨房機器、美容室ならドライヤーなど、求められる電力が異なるからです。
今は「スマート分電盤」という新しいタイプも登場し、電力の使い方を見える化できるようになっています。
分電盤を見直すことは、安全のためだけでなく、設備の安定稼働や将来のトラブル防止にもつながります。
分電盤は“電気を分けるコントロールセンター”
お店の中で使う電気は、ひとつの回線で一気に届けられているわけではありません。
照明、冷蔵庫、厨房機器、空調など、それぞれの設備に合わせて電気を分けて送ってくれているのが「分電盤」です。
分電盤は、例えるなら電車が分かれる駅のようなもの。
駅に到着した電力が、それぞれの路線=回路に振り分けられて、必要な設備に届いています。
もし一部にトラブルが起きても、他の設備は止まらずに使い続けることができます。
また、分電盤の中には「主幹ブレーカー」と「子ブレーカー」があり、それぞれ役割が違います。
全体の元栓のような役割をする主幹と、設備ごとの安全を守る子ブレーカーがあることで、店舗全体を安全に保つ仕組みができています。
分電盤は、建物に入ってきた電気を照明や厨房機器、空調などに分けて送るための装置です。
店舗内の設備ごとに、必要な量の電気を安全に届ける役割を担っています。
この仕組みをイメージしやすくすると、分電盤は「電気の駅」のような存在です。
電力会社から届いた電気は、いったん駅(分電盤)に入り、そこから「照明行き」「冷蔵庫行き」「レジ行き」といった路線(回路)に振り分けられます。
それぞれの電気は別々の線で運ばれ、店舗内の各設備へと届けられているのです。
以下は、設備と電気の流れの一例です。
| 回路名 | 接続されている主な設備 |
| 照明回路 | 天井照明、看板照明など |
| 空調回路 | エアコン、換気扇など |
| 厨房回路 | IHコンロ、電子レンジ、冷蔵庫など |
| コンセント回路 | レジ周辺、スタッフ用電源、PCなど |
こうして分かれていることで、たとえば厨房機器にトラブルが起きても、その回路だけを止めれば対応できます。
他の照明や空調、レジなどはそのまま使い続けられます。
店舗の営業を続けながら、必要な修理だけを行うことが可能です。
電気の流れが分かれているかどうかで、トラブル時の影響範囲は大きく変わります。
分電盤は、店舗の営業を守るために欠かせない存在です。
店舗や施設の分電盤には、複数のブレーカーが組み込まれています。
そのなかでも、よく使われるのが「主幹ブレーカー」と「子ブレーカー」です。
どちらも電気の流れをコントロールする装置ですが、役割には明確な違いがあります。
主幹ブレーカーは、建物全体の電気をまとめて管理する“元栓”のような存在です。
電気の入り口にあり、大きなトラブルが起きたときには、すべての電気を止めて建物を守ります。
一方の子ブレーカーは、設備ごとの回路に設置されています。
照明用、厨房機器用、空調用といったように、エリアや用途ごとに細かく分けて制御できるのが特徴です。
次の表に、それぞれの役割と動作の違いをまとめました。
| ブレーカーの種類 | 主な役割 | 作動する場面 |
| 主幹ブレーカー | 全体の電気をまとめて管理する | 建物全体の異常・漏電など |
| 子ブレーカー | 設備やエリアごとの電気を管理する | 特定の回路で異常や過電流が発生時 |
たとえば、厨房の機器に電気の異常が起きた場合。
その機器につながっている子ブレーカーだけが自動で電気を止めてくれます。
でも照明やレジなど、別の設備はそのまま使い続けることができます。
もしもブレーカーが1つしかなかったら、電気のトラブルが1カ所だけでも、店じゅうの電気が全部止まってしまいます。
レジも消え、照明も落ち、営業がストップしてしまうかもしれません。
設備ごとにブレーカーが分かれていることで、影響を受けるのは「問題が起きた場所だけ」です。
お店全体へのダメージを最小限に抑えることができるのです。
分電盤がないとどんなトラブルが起きる?
分電盤は、建物の中で電気を安全に管理し、必要な場所に分けて届けるための装置です。
普段はあまり意識しないかもしれませんが、不具合や設計ミスがあるとさまざまなトラブルにつながります。
とくに注意したいのは、設備の増設や経年劣化による「容量オーバー」です。
電気の使いすぎでブレーカーが何度も落ちるようになると、営業中でも突然機器が使えなくなります。
また、漏電(※電気が本来の配線以外に流れてしまう現象)が起きれば、感電や火災につながる危険もあります。
以下は、分電盤に問題があるときに起きやすいトラブル例です。
| 想定されるトラブル | 影響 |
| ブレーカーが頻繁に落ちる | 電気が止まり、機器や営業に支障が出る |
| 漏電 | 感電・火災など、人や設備に危険が及ぶ |
| 店舗全体の停電 | 主幹ブレーカーが落ち、全設備が停止 |
| 機器の劣化 | 過負荷が続き、寿命が短くなることも |
こうしたトラブルは、目に見えないうちに少しずつ進行していることがあります。
「特に不便はないから大丈夫」と思っていても、実は限界が近づいていることもあります。
定期的な点検や、設備に合った分電盤の設計・交換を行うことで、思わぬ営業停止や機器故障のリスクを避けることができます。
電気トラブルは予兆があるうちに見つけておくことが大切です。
「気になったときが見直しのチャンス」と考えて、今の状態を一度チェックしてみましょう。
漏電とは、電気が本来の配線から外れて、壁の中や金属部分など意図しない場所に流れてしまう状態です。
そのまま放置すると、感電や火災、電気機器の故障といった深刻なトラブルにつながるおそれがあります。
特に湿気の多い厨房や築年数の古い建物では、漏電のリスクが高まります。
こうした異常は、自分で確認することができないため、調査には必ず電気工事士の資格を持った業者への依頼が必要です。「焦げくさいにおいがする」「ブレーカーがよく落ちる」といった小さな異変も、早めに相談することが大切です。
▶︎参考|漏電改修工事は電気工事士の資格保有者のみが実施可能(電気工事士法第3条)
店舗ごとに分電盤の設計をカスタマイズするメリット
店舗の分電盤は、どこでも同じというわけではありません。
店舗の業種によって、必要な電気の量や使い方がまったく違うため、設計は「カスタマイズ」する必要があります。
設計段階で店舗に合った電気回路を組んでおくことで、安全性と効率性が大きく変わってきます。
以下は、主な業種ごとに異なる電力ニーズの一例です。
| 業種 | 主な電気使用機器 | 設計のポイント |
| 飲食店 | 冷蔵庫、食洗機、加熱機器など | 大容量の電力供給と複数回路の確保 |
| 美容室 | ドライヤー、ホットカーラーなど | 高出力機器対応と瞬間負荷の分散 |
| 物販店 | 照明、空調、レジ機器など | 安定供給と回路の整理 |
たとえば飲食店では、複数の厨房機器を同時に使うことが多いため、回路が足りないとブレーカーが落ちやすくなります。
美容室では、一斉にドライヤーを使うと一時的に電力が集中するため、分散設計が求められます。
物販店では、強い電力は必要なくても、日中ずっと安定して使える設計が大切です。
こうした業種ごとの特徴を踏まえて分電盤を設計してもらいましょう。
無駄な電力消費を減らせたり、設備トラブルのリスクを減らしたりできます。
また、必要な時にすぐに電気を使えることが、スムーズな営業の助けにもなります。
開業当初は問題がなくても、機器を追加したときに容量オーバーになることもあります。
そのため、将来的な機器追加も見越した「余裕ある設計」をしておくことが重要です。
設計の見落としがあると、後から再工事が必要になる場合もあります。
業者に相談しながら進めていく際にも、将来的な要望も伝えてみても良いかもしれません。
+α情報:スマート分電盤という新しい選択肢
分電盤にも“スマート化”の波が来ています。
「スマート分電盤」は、電気の使い方をリアルタイムで見える化し、トラブル予防や省エネにも役立つ新しい設備です。
これまでの分電盤との違いは、ただ配電するだけでなく「電気の状態を把握し、管理できる」点にあります。
以下は、スマート分電盤で利用できる主な機能とその特徴です。
| 機能 | 内容 |
| 電力の見える化 | どこでどれだけ電気を使っているかをリアルタイムで表示 |
| 異常の予知通知 | 過電流・漏電・過熱などを検知してアラートを発信 |
| 遠隔操作 | 外出先からブレーカーの確認・制御が可能 |
| データ蓄積 | 電力使用量や異常履歴を自動で記録・分析 |
たとえば、冷蔵庫の使用電力が普段より急に増えた場合。
通常なら見過ごしてしまいがちですが、スマート分電盤なら通知が来て、機器の異常に早く気づけます。
また、複数店舗を運営している場合でも、遠隔から電気の状況を把握できるため、管理の手間が大幅に減ります。
このような仕組みは、省エネ対策にも有効です。
どの設備が電力を多く消費しているかが明確になれば、電気代のムダを見直すきっかけにもなります。
災害が起きたときでも、スマート分電盤は電気の異常をすぐに知らせてくれます。
万が一の火災や漏電も、早く気づくことで被害を抑えられる可能性が高まります。
電気のムダづかいを見直せたり、何かあったときにすぐ対応できたりと、長く使うほど安心につながる設備として注目が高まっています。

分電盤は、電気を安全に届けるための要となる設備です。
けれど、多くの店舗では一度設置してしまうと、普段はあまり意識されることがありません。
だからこそ、「いつ交換するの?」「何を見て判断するの?」と迷う方も多いはずです。
たとえば、ブレーカーがよく落ちる、分電盤まわりが熱い・焦げ臭い、設置から10年以上経っている。
そんなときは、分電盤の容量不足や劣化が進んでいる可能性があります。
また、新しい厨房機器やエアコンを導入した、レイアウト変更で電気設備が増えた。
そんな“変化のタイミング”こそ、分電盤の見直しをしておきたい場面です。
電気の使い方が変われば、必要な「通り道」=容量も変わってくるからです。
分電盤工事と聞くと、大がかりで時間がかかる印象があるかもしれません。
ですが、事前にチェックしておくことで、工事の規模も費用も抑えられるケースがほとんどです。
ここでは、交換の目安となるサインや、点検しておくと安心なポイントをわかりやすくご紹介します。
これから新しい設備を増やす方も、なんとなく不安を感じていた方も、店舗の“電気の健康診断”としてぜひお役立てください。
こんな症状が出たら分電盤の交換サインかも
設備に大きな不具合がなくても、日常の中でふと「何か変だな」と感じる瞬間があるかもしれません。
分電盤にも、そんな違和感から始まる変化があります。
たとえば、ブレーカーがよく落ちる。
分電盤のまわりが熱を帯びていたり、焦げたようなニオイがする。
あるいは、設置から10年以上が経っている。
こうした小さなサインは、設備の老朽化や容量不足の可能性を教えてくれているのかもしれません。
どれも「すぐに故障」とまではいかなくても、将来のトラブルの芽になることがあります。
交換や点検の目安として、頭の片隅に置いておくだけでも、いつかの変化に気づきやすくなります。
大切なお店を、長く安心して使い続けるためのヒントとして、覚えておきましょう。
ブレーカーが落ちるたびに、業務が中断したり、機器の再起動に手間がかかったり。
「またか……」と感じながら、そのまま使い続けている方も多いかもしれません。
でも実は、ブレーカーが頻繁に作動するのは、電気まわりに何らかの“サイン”が出ている可能性があります。
そのまま放置してしまうと、より大きなトラブルや設備の損傷につながることもあるため、原因を知っておくことはとても大切です。
ブレーカーは、異常な電流が流れたときに自動で電気を止める「安全装置」です。
過剰な電気が流れることで火災や機器の故障が起きるのを防いでくれます。
しかし、落ちる頻度が高い場合は、電気の使いすぎや、分電盤(電気を分けて配る設備)の劣化が原因になっていることもあります。
特に、厨房機器や空調設備など高出力の機器を後から増やした場合、想定していた容量を超えてしまっているケースも少なくありません。
| よくある原因 | 考えられる背景 | 対処の方向性 |
| 一部の機器を使うと落ちる | 容量オーバー、回路設計の不足 | 回路分け・容量見直し |
| 一日に何度もブレーカーが落ちる | 電気の使用量が設計以上になっている | 分電盤や配線の点検・更新 |
| 機器を増やしてから落ちやすい | 新しい機器が想定より電力を使っている | 分電盤の容量アップ検討 |
| ブレーカー自体が古い | 経年劣化で感度が不安定になっている | ブレーカー・分電盤の交換 |
「なんとなく不便だけど、まあ大丈夫だろう」と見過ごしがちな症状も、実は見直しのタイミングかもしれません。
少しでも気になることがあれば、早めに確認しておくことで、安心して店舗運営を続けることができます。
分電盤に近づいたとき、「ちょっと焦げたようなニオイがする」「本体が熱く感じる」といった違和感に気づいたことはありませんか。
こうした変化は、内部で起きているトラブルのサインかもしれません。
気のせいだと思って放っておくと、思わぬ事故につながる可能性もあります。
焦げ臭や異常な熱の原因としては、配線の接触不良や内部部品の焼損などが考えられます。
これらは目で見えない部分で進行していることが多く、発見が遅れると発火のリスクが高まります。
以下に代表的な症状と、その対応目安をまとめました。
| 症状 | 想定される原因 | 対応の目安 |
| 本体に触れたときに熱い | 回路の過負荷、接触不良 | 早めに点検を依頼 |
| 焦げ臭がする | 内部での焼損や漏電 | すぐに使用を中止し相談 |
| 焦げたような変色が見える | 部品の劣化、熱による変形 | 分電盤交換の検討が必要 |
たとえば、厨房近くの分電盤で熱を帯びた状態が続いていると、湿気や油分と組み合わさって発火の可能性が高くなります。
また、ニオイや見た目の変化は、設備が限界に近づいているサインでもあります。
気になる症状に気づいたときは、無理に触らず、電気工事の専門業者へ相談しましょう。
「古い設備だけど、まだ使えているから大丈夫」
そんなふうに感じている方もいるかもしれません。
実際、目に見える不調がなければ、分電盤の状態を気にする機会はあまりないかもしれません。
けれども、分電盤は10年を超えると、内部の部品や配線の劣化が徐々に進みはじめます。
それによって、思いもよらないトラブルのきっかけになることがあります。
分電盤の交換や見直しは、「何かが起きてから」ではなく、「何も起きていないうちに」行うのが理想です。
以下は、使用年数による状態の目安をまとめたものです。
| 使用年数の目安 | 状態の変化とチェックポイント |
| ~10年未満 | 大きな問題は少ないが、点検は年1回程度で安心 |
| 10~15年 | 絶縁劣化・部品の摩耗が進み、交換の検討が必要に |
| 15年以上 | 火災や漏電のリスクが高まり、早急な交換が推奨される |
たとえば、長年使い続けた分電盤の内部では、目に見えない部分で熱による劣化や接触不良が起きていることがあります。
古いタイプの分電盤では、現在の安全基準を満たしていないケースもあり、万が一の事故につながる可能性も否定できません。
一方で、定期点検を受けておくことで、まだしばらく使えるのか、そろそろ交換すべきかが把握できるようになります。
定期的なチェックは、大がかりな工事や営業への影響を避けるための備えにもなります。
分電盤は長く使うものだからこそ、「まだ大丈夫」と思えるうちに、状態を確認しておくことが大切です。
点検を通じて現状を知っておくことで、将来の不安をひとつ減らすことができます。
古い分電盤を使い続けるとどうなる?
古くなった分電盤は、内部の部品が劣化し、絶縁性能(電気を漏らさない力)が落ちている可能性があります。
また、サビやホコリの蓄積によって接触不良が起きたり、電気の流れが不安定になったりすることもあります。
安全面だけでなく、電力ロスが発生して無駄な電気代がかかっているケースも少なくありません。
以下は、古い分電盤に見られる主なリスクです。
| 項目 | 内容 |
| 経年劣化 | 絶縁の劣化・接点の摩耗・錆びなどが進行 |
| 火災・漏電リスク | 内部の劣化によりトラッキングや過熱が発生 |
| 法令・規格の不適合 | 古い分電盤は現行の安全基準に合っていないことも |
| 電気のムダ使い | 効率の悪い配線や機器による電力ロス |
| 修理対応の難しさ | 古い型の部品が入手困難で、修理できないことも |
たとえば、昔の設備基準でつくられた分電盤では、今のように多くの電気機器を同時に使う状況に対応できないことがあります。
さらに、古い部品はメーカーの生産終了により修理が難しくなっていることもあります。
とくに、今後設備の増設やリニューアルを予定している場合は、事前に見直しておくことで、安心して店舗運営を続けることができます。
古い分電盤は、電気の流れが非効率になっていたり、余計な熱を発していたりと、見えない負担が積み重なっているかもしれません。
容量不足で営業に支障が出る前にできること
日々の営業をしている中で、ふと「なんだか最近、電気が不安定かも…」と感じたことはありませんか。
複数の厨房機器を使うとブレーカーが落ちたり、エアコンや冷蔵庫が一瞬止まったり。
そのたびに作業が中断されたり、お客様への対応が遅れてしまったりすると、少しずつストレスが積み重なりますよね。
こうしたトラブルの背景には、分電盤の容量不足が隠れていることがあります。
開業当初から設備を少しずつ増やしてきた店舗では、気づかないうちに電気の通り道が足りなくなっている場合があります。
目に見えない部分だからこそ、つい後回しになりがちですが、「なんとなく気になる」という感覚は、早めに見直すきっかけになります。
以下は、容量不足のサインとしてよく見られるポイントです。
| 気づきのヒント | 内容 |
| ブレーカーがよく落ちる | 機器の同時使用で急に電気が切れることが増えた |
| 一部機器が不安定に動作する | エアコン・冷蔵庫・照明などが一瞬止まるなど |
| 設備を増やす予定がある | 厨房機器や空調機器を新たに導入しようとしている |
| 分電盤が古い | 開業から10年以上、電気設計を変えていない |
もし心当たりがある場合は、いまの設備に対して分電盤が適しているか、一度チェックしてみるのがおすすめです。
特に今後、新しい機器の導入を予定しているなら、電気工事士の資格を持ったプロに相談しておくと安心です。
無理のない配線設計を提案してくれるほか、電気代を抑える方法や節電のアイデアを教えてくれることもあります。
「ちょっと気になるな」と感じたタイミングこそ、見直しのチャンス。
余裕をもって対策しておくことで、日々の営業を落ち着いて続けることができるはずです。

店舗で使う電気のこと、つい「今のままで足りてるし」と思ってしまいがちです。
オープン当初と比べて、いつのまにか設備や電気機器が少しずつ増えていませんか?
たとえば、IHコンロや業務用の冷蔵庫を導入したり。
夏場の暑さ対策にエアコンを追加したり。
お客さま対応の効率化で、電気を使う機器を同時に動かす場面が増えていたり。
小さな変化の積み重ねが、電気の通り道(容量)を少しずつ圧迫しているかもしれません。
気づかないうちに容量の上限を超えてしまうと、ブレーカーが落ちたり、機器が止まったりと、業務に思わぬ支障が出ることもあります。
築年数が経った建物では、配線や分電盤自体が古く、今の使用状況に合っていないケースも少なくありません。
そんなときに一度検討して頂きたいのが「電気容量の見直し」です。
必要な電気を、必要なだけ安心して使えるようにすることで、営業中のトラブルを減らすだけでなく、将来の機器追加にも柔軟に対応できるようになります。
「まだ困ってはいないけど、ちょっと気になる」。
そんなときが、実は見直しのいいタイミングかもしれません。
店舗をこれからも安心して使い続けるために、電気の通り道を見直すきっかけにしてみてください。
容量アップってなに?“電気の通り道”の話
「容量アップって、そもそも何を増やすこと?」と感じる方もいるかもしれません。
これは、店舗で一度に使える電気の量(契約容量)を広げることを意味します。
イメージとしては、水道のパイプに似ています。
細いままだと、一度にたくさんの水(=電気)を流すことはできません。
設備が増えたり、同時に複数の機器を使う場面が増えれば、その“電気の通り道”を太くしてあげる必要があります。
ただし、容量を増やすには分電盤や配線の見直しも必要になることがあります。
建物によっては、現在の設計が新しい機器に合っていない場合も。
容量の考え方を知っておくだけでも、設備を追加する際の判断がしやすくなります。
店舗の設備をアップデートすることは、サービス向上や業務効率のために大切なことです。
しかし、新しい機器を導入するたびに、見えないところで電気の負担が大きくなっていることに気づきにくいかもしれません。
とくに、IH調理器や製氷機、業務用冷蔵庫などは、消費電力が大きい機器にあたります。
こうした機器を導入する場合、通常よりも電気を多く使うため、専用の配線(専用回路)が必要になることもあります。
また、これらの機器をほかの電気設備と同時に使用することで、店舗全体の電気容量の上限を超えてしまう可能性もあります。
すると、ブレーカーが落ちたり、機器の誤作動が起きるなど、営業に支障をきたすケースも出てきます。
以下は、導入時に注意が必要な機器の一例です。
| 機器名 | 主な特徴 | 注意ポイント |
| IH調理器 | 高火力・瞬間出力が大きい | 200V専用回路が必要なことも |
| 製氷機 | 長時間連続稼働 | 消費電力が意外と大きい |
| 業務用冷蔵庫 | 24時間稼働 | 常に電力を消費し続ける |
| 電子レンジやオーブン | 瞬間的な高出力 | 同時使用で負荷集中の可能性 |
たとえば、新しい機器を増やすときは、「今ある分電盤や容量でまかなえるか」を一度見直すのがおすすめです。
業種によっては、日々使う電気機器の量や出力がとても大きくなります。
飲食店、美容室、工場などは、まさにその代表です。
たとえば、飲食店の厨房では、IH調理器や冷蔵庫、食洗機など複数の機器を同時に使います。
美容室ではドライヤーやスチーマー、給湯設備が一気に稼働することがあります。
工場ではモーターやコンプレッサー、換気設備などが常時動いているケースも少なくありません。
こうした業種では、想像以上に「電気の通り道」に負荷がかかっているのです。
とくに注意が必要なのが、業務用エアコンなどの高出力機器です。
一台あたり10〜20kWの電力を消費することもあり、回路ごとの負担が偏るとブレーカーが落ちたり、電圧が不安定になる原因にもなります。
以下は、高出力機器を多く使う代表的な業種とその特徴です。
| 業種 | 使用機器の例 | 注意ポイント |
| 飲食店 | IH調理器、冷蔵庫、フライヤー | 同時使用が多く、負荷が集中しやすい |
| 美容室 | ドライヤー、スチーマー、給湯器 | 瞬間的に高出力になる機器が多い |
| 工場 | 溶接機、コンプレッサー、換気装置 | 稼働時間が長く、常時高負荷になる |
これらの業種では、使用機器の種類や使い方をふまえて、分電盤の回路設計や電気容量の見直しが必要になることがあります。
店舗の設備を更新するとき、見落とされがちなのが「電気の通り道」の状態です。
とくに築年数の経った建物では、分電盤や配線が当時のままということもあります。
そこに新しい機器を追加すると、思わぬ不具合やリスクが生じることがあります。
古い設備には、今の電力需要に対応しきれない部分があります。
たとえば、アルミ配線は現在主流の銅線よりも電気の流れが悪く、発熱しやすい特性があります。
また、経年劣化によって絶縁性能が低下し、接続部にゆるみや腐食が見られるケースもあります。
こうした状態のまま高出力の機器を追加すると、配線に無理がかかり、ブレーカーの作動や発煙、最悪の場合は火災のリスクにもつながります。
以下は、古い建物で注意が必要なポイントの一例です。
| 注意すべきポイント | 内容 | 想定されるリスク |
| 古い配線(例:アルミ線) | 導電率が低く、熱を持ちやすい | 発熱、絶縁劣化 |
| 絶縁体の劣化 | 長年の使用で脆くなっている | 漏電、ショートの可能性 |
| 分電盤の老朽化 | 回路構成が古く容量が足りない | ブレーカー落ち、設備停止 |
もし新しい機器の導入を検討しているなら、設備の「受け皿」となる電気まわりも一緒に見直しておくことがおすすめです。
必要に応じて電気工事士に相談すれば、今後の運用に合った提案や容量アップの判断もしてもらえます。
設備の入れ替えは、電気環境を整える絶好のタイミングでもあります。
容量不足が原因で起きる日常のトラブル
ブレーカーが突然落ちたり、いつも使っている機器が急に止まったり。
そんな「ちょっと困ったこと」が、思いがけず頻発するようになっていませんか。
もしかするとそれは、電気の容量が足りなくなってきているサインかもしれません。
容量不足とは、店舗内で同時に使う電気が「契約している上限」を超えてしまう状態のことです。
使う電気の量がオーバーすると、ブレーカーが作動して電気が止まったり、照明がちらついたり、空調が動かなくなったりといったトラブルにつながります。
設備そのものの故障ではなく、通れる電気の「道」が混雑している状態だとイメージするとわかりやすいかもしれません。
以下に、容量不足が原因で起きやすい日常のトラブルをまとめました。
| トラブルの例 | 起きやすい場面 |
| ブレーカーが頻繁に落ちる | 電気機器を同時に多く使ったとき |
| 機器が急に停止する | 調理中・精算中などピーク時 |
| 照明がちらつく | 他の機器が稼働しているとき |
| 空調が止まりやすくなる | 夏場や冬場のフル稼働時 |
このようなトラブルは、一つひとつは小さく見えても、日常業務にストレスや支障を与えます。
「設備のせいかな?」と思っていたことが、実は電気容量の問題だったというケースも多いのです。
少しでも心当たりがあるなら、一度専門業者に相談して、容量が足りているかチェックしてもらうと安心です。
電気容量アップで得られる3つの安心ポイント
電気容量をアップすると、まず日々の営業がスムーズになります。
ブレーカーが落ちにくくなり、設備が安定して動くことで、作業の中断やお客様への影響も最小限に抑えられます。
「突然止まるかもしれない」という不安が減ることで、落ち着いて店舗運営に集中できます。
また、安全性の面でも安心感が高まります。
容量不足のまま使い続けると、配線や分電盤に余計な負担がかかり、発熱や劣化のリスクが高まります。
容量を見直すことで、こうしたトラブルの芽を早めに摘むことができます。
火災や漏電といった重大な事故のリスクも下がります。
さらに、将来的な設備追加にも余裕をもって対応できるようになります。
店舗の成長に合わせて新しい機器を導入しても、容量に余裕があれば安心です。
毎回の配線変更やブレーカーの調整をしなくて済み、コスト面や作業面でも効率的です。
表:電気容量アップで得られる安心ポイント
| ポイント | 効果・メリット |
| 営業の安定性 | 機器の停止やブレーカー落ちが起きにくくなる |
| 安全性の向上 | 過負荷や発熱を防ぎ、火災・漏電のリスクを減らせる |
| 将来の柔軟性 | 設備追加やリニューアルにも余裕をもって対応可能 |
もし、「これから機器を増やす予定がある」「ブレーカーが落ちたことがある」という方は、今の設備に合った容量になっているか一度チェックしてみるのがおすすめです。

分電盤工事と聞くと、「費用が高そう」「どんな作業をするのか分からない」と、少し身構えてしまうかもしれません。
でも実際は、設備の安全性を保ったり、これからの店舗運営に備えたりするうえで、とても身近な工事のひとつです。
とくに電気をよく使う業種や、築年数の経った建物では、思わぬトラブルを防ぐためにも早めの見直しが安心につながります。
とはいえ、「どれくらい費用がかかるの?」「営業しながらできる?」といった疑問があるのも当然です。
そこでこのセクションでは、分電盤工事にかかるおおよその費用や内訳、実際の工事の流れ、営業中に工事を進めるための工夫などを、わかりやすく整理しました。
事前に知っておくことで、業者との打ち合わせもスムーズになり、不要な出費や営業への影響も減らすことができます。
大切なのは、「知らないから不安」のままにせず、「知って準備できている」状態にしておくこと。
この記事を通じて、工事の全体像をつかみ、自分の店舗にとって必要な対応を前向きに考えるヒントになればうれしいです。
配線作業は「電気工事士」の資格が必要です。
これは電気工事士法第3条第1項及び第2項に規定されています。
違反した場合、3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられます。
一般家庭には100〜200Vの電流が流れています。
電流は取り扱いによっては感電や火事などの命に関わる危険性があります。
知識がないまま配線に触れるのは大変危険です。
そのため法律で専門の資格を持った電気工事士が行うことが定められています。
参考情報|経済産業省 電気工事士法(昭和35年8月1日法律第139号)の逐条解説 (令和5年11月版)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujisichikujyou.pdf
参考情報|電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第14条
分電盤工事にかかる費用の目安と内訳を知ろう
分電盤工事を考えたときに、まず気になるのはやはり「いくらかかるのか」ではないでしょうか。
工事費用は店舗の広さや設備の状況によって変わりますが、あらかじめ目安を知っておくと安心です。
見積もり内容の内訳がわかれば、不要な費用を見抜く手助けにもなります。
たとえば本体やブレーカーなどの機器代、配線作業や設置費用、出張費や廃棄費用などが基本的な項目です。
さらに、営業しながら工事を行う場合は仮設電源の設置費や、夜間・早朝の作業にかかる割増料金が追加されることもあります。
これらは業者によって設定が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。この章では、見積もりの中身をわかりやすく整理しながら、想定外の出費を防ぐためのヒントをご紹介します。
まずは全体像を知って、納得感のある工事計画を立てるところから始めましょう。
分電盤工事を考えるとき、やはり最初に気になるのは「費用がいくらくらいかかるのか」という点です。
見積書を見ても、どこにどれだけの費用がかかるのかがわかりづらいと、不安に感じることもありますよね。
ここでは、代表的な費用の内訳と相場を、やさしく整理してみましょう。
| 項目 | 目安金額 | 内容 |
| 機器代 | 2〜10万円 | 分電盤本体やブレーカー代 |
| 工事費 | 2〜10万円 | 設置・配線調整・動作確認など |
| 出張費 | 1,000〜5,000円 | 業者の移動費用 |
| 廃棄費 | 2,000〜5,000円 | 古い分電盤の処分費 |
選ぶ機器の性能や、建物の状況によって金額は前後します。
また、業者によって費用の考え方や含まれる内容が異なる場合もあります。
とくに工事費は、配線の距離や作業時間によっても変わってくるため、相場はあくまで目安としてとらえておくのがおすすめです。
おおまかな目安としては、全体で5万〜15万円ほどになることが多いですが、
複数の回路があったり、特殊な仕様が必要な場合は20万円を超えることもあります。
もし不安な点がある場合は、遠慮なく見積もりを依頼してみましょう。
項目ごとの説明を受けるだけでも、費用への理解がぐっと深まり、安心して進められるはずです。
自分のお店にとって必要な工事なのかどうかを見極めるためにも、早めにプロに相談しておくことがポイントです。
分電盤の交換や容量アップを検討していると、見積もりの中に「仮設電源費」や「夜間作業費」といった項目が入っていて驚くことがあります。
これは工事を営業中に行う場合や、営業時間外の作業を希望する場合にかかる追加費用です。
本来の工事費とは別に発生するものなので、事前に確認しておくことが大切です。
| 項目 | 費用の目安 | 内容・備考 |
| 仮設電源 | 1〜3万円 | 営業中に冷蔵庫やレジを止めないための一時電源設置費 |
| 夜間・早朝工事 | 通常費の20〜50%増 | 店舗の営業時間外に対応する場合の割増料金 |
| テナント手続き | 無料〜数千円 | 管理組合への届け出や許可申請が必要なケースも |
たとえば、飲食店や美容室など、営業時間中に工事を避けたい場合は夜間作業になることがあります。
また、冷蔵設備やレジの稼働を止められない業種では、仮設電源を用意することで営業を止めずに済むケースもあります。
こうした対応はとても助かりますが、当然そのぶん費用が加算されるため、あらかじめ業者に追加項目について相談することがポイントです。後から「そんな費用もかかるなんて知らなかった」とならないように、見積もりの内訳をよく見て、不明な点は遠慮なく聞いてみましょう。
追加費用を含めて全体像を把握しておくことで、安心して工事を進めることができます。
工事の進め方とスケジュール感を確認しよう
分電盤の工事は、段取りをしっかり把握しておけば、店舗運営と両立しながらスムーズに進められます。
実際には半日〜1日で終わることも多く、営業を止めずに対応できるケースもあります。
ここでは、工事の一般的な流れとスケジュールの目安を紹介します。
| 工程 | 内容 |
| 現地調査 | 設備の確認や希望内容のヒアリング |
| 見積もり提示 | 必要な作業・費用・追加オプションの案内 |
| 日程調整 | 営業時間外や休業日を優先して調整 |
| 工事実施 | 小規模店舗なら半日〜1日で完了することが多い |
| 動作確認 | ブレーカーや機器の通電を確認して完了 |
たとえば、小さな飲食店や美容室であれば、半日〜1日以内で終わるケースがほとんどです。
ただし、建物が古くて配線が複雑な場合や、複数回路にわたる作業が必要な場合には、2日以上かかることもあります。
当日はブレーカーの位置や、使用している主要な機器を把握しておくと、業者とのやりとりがスムーズになります。
工事を依頼する前に、希望する日程や休業の有無を伝えておくことも大切です。
見積もり時にスケジュールの相談をしておけば、営業への影響を最小限に抑えながら工事を進めることができます。
安心して店舗運営を続けるためにも、事前の段取りがポイントとなります。
営業中でも工事できる?工夫と対策を紹介
分電盤の工事と聞くと「営業は止めなきゃいけないのかな」と心配になるかもしれませんが、実は工夫次第で営業を続けながら進めることも可能です。
「思っていたより柔軟にできそう」と感じてもらえたら、前向きに工事を検討するきっかけになります。
ここでは、営業中でも進めやすくなる工夫をご紹介します。
| 工夫の種類 | 内容 | 効果 |
| 分割工事 | 回路ごとに午前・午後に分けて工事する | 一部設備だけを止めて対応可能 |
| 仮設電源 | レジや冷蔵庫などに一時的に電源を供給 | 最小限の設備は動かし続けられる |
| 優先順位リスト | 使用する機器をあらかじめ整理して伝える | 工事中も必要な機器を優先して稼働できる |
たとえば「冷蔵庫だけは止めたくない」「レジだけ動かしたい」といった希望も、事前に伝えておくことで対応できる場合があります。
仮設電源を使えば、必要な機器だけを選んで動かすこともできますし、回路ごとに分けて工事する方法もあります。
実際には、工事の内容や設備の状況によって対応の可否は変わります。
気になる場合は、見積もりの段階で「営業中でも可能か」を相談してみてください。
店舗の営業を大切にしながら、スムーズに工事を進める方法が見つかるかもしれません。

店舗にとって電気設備は、ふだん意識しないけれど大切な存在です。
分電盤を見直すことで、日常のトラブルや不安がぐっと減り、安心して営業を続けられるようになります。
たとえば、エアコンや冷蔵庫が止まらずに安定して動く。
ブレーカーが落ちるストレスがなくなる。
そんな日常が整うだけで、接客や作業に集中できる環境が生まれます。
さらに、今後の機器追加やリニューアルを予定している方にとっても、容量アップや工事の準備は将来の安心につながります。
無理なく、計画的に店舗を育てていくための一歩です。
分電盤の見直しや点検は、専門の電気工事士(国家資格保有者)にご相談いただくことで、状況に合った提案を受けることができます。
今もこれからも、店舗が安全に、そして安定して営業を続けられますように……
まずは「気になるな」と思った今が、相談のきっかけかもしれません。
分電盤の点検や見直しについて、どうぞお気軽にご相談ください。
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
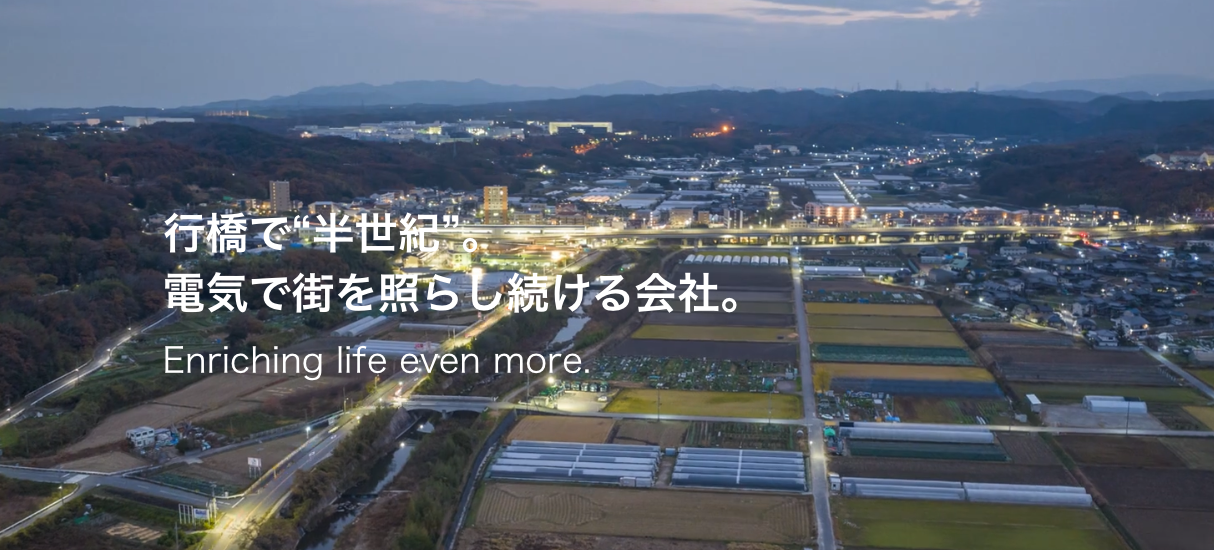
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
 電気工事メディア
電気工事メディア

