新しい厨房機器を導入したいけれど、「今の電気容量で動くのだろうか」と不安に感じたことはありませんか。
居抜き物件を引き継いだ方の中には、「前のお店の配線をそのまま使って大丈夫なのか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
また、開業準備を進めるなかで、「保健所や消防の検査で、電気まわりは何を確認されるんだろう」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
飲食店の厨房では、業務用のオーブン、フライヤー、食洗機、大型冷蔵庫など、たくさんの機器が同時に稼働します。
これらの機器は家庭用とは違い、200Vの電源や専用回路が必要になることも多く、事前の計画が欠かせません。
適切な電気工事を行うことで、機器が安定して動き、調理がスムーズに進むようになります。
LED照明や高効率機器を取り入れれば、日々の電気代を抑えることもできます。
そして何より、安全基準をしっかり満たすことで、長く安心して営業を続けられる環境が整います。
この記事では、厨房の電気工事について、基本的な知識から実際の進め方まで、丁寧に整理してお伝えします。
新規開業の方も、改装を検討中の方も、今の厨房をより良くしたい方も、次の一歩を安心して踏み出せるお手伝いができればと思います。

株式会社 林田電気工業
林田竜一
代表取締役
行橋市で電気工事会社を経営しています。お客様ひとりひとりに丁寧に対応し、電気でつなぐ明るい未来をスローガンに地域に貢献できるように努めています。
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
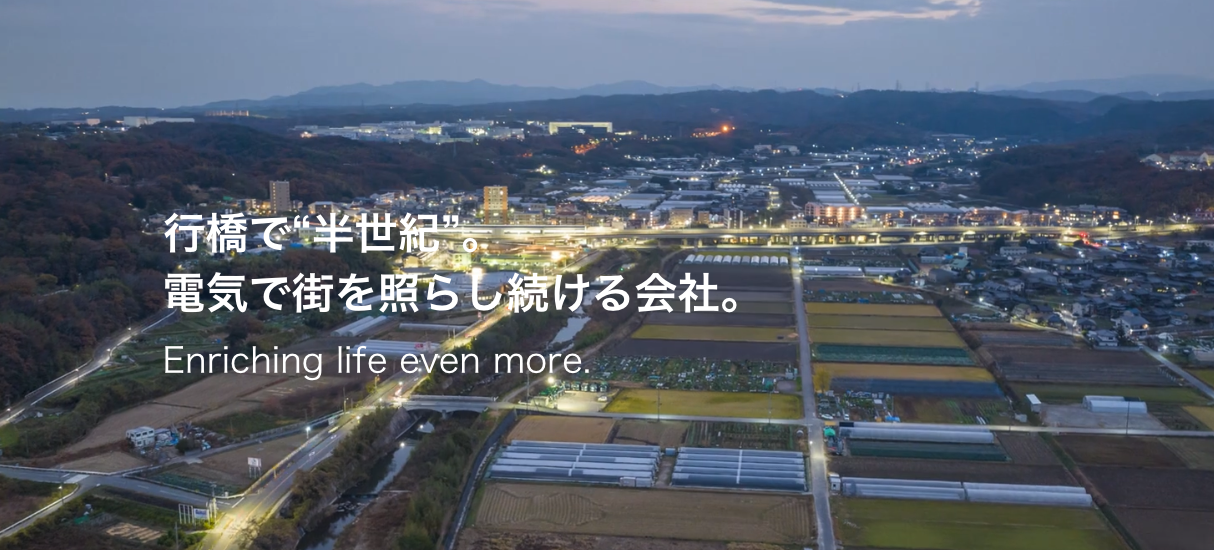
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

飲食店の厨房には、オーブンやフライヤー、食洗機、大型冷蔵庫など、たくさんの機器が並びます。
これらの機器を安全に、そして快適に使うためには、適切な電気工事が欠かせません。
家庭のキッチンとは違い、業務用の機器は消費電力がとても大きく、専用の電源や回路を用意する必要があります。
「電気工事って、何から考えればいいんだろう」と感じる方も多いかもしれませんね。
実は、厨房の電気工事には、大きく分けて「設備の種類」「電源の選び方」「守るべき法令やルール」という3つのポイントがあります。
この3つを押さえておくことで、開業や改装の準備がスムーズに進みやすくなります。
新しくお店を開く方も、居抜き物件を引き継ぐ方も、すでに営業中で設備を見直したい方も、安心して次のステップに進めるように、ここから一つひとつ丁寧に見ていきましょう。
厨房の電気工事は難しく感じるかもしれませんが、基本を知っておくだけで、業者さんとのやりとりもぐっとスムーズになります。
飲食店の厨房の電気工事で扱う設備と範囲
厨房の電気工事と聞くと、「コンセントや照明の工事かな」とイメージする方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、それだけではなく、調理機器を動かすための動力電源、換気設備、空調設備、さらには安全を守るための設備まで、幅広い工事が含まれます。
ここでは、厨房の電気工事で扱う主な設備と、それぞれの役割を整理してお伝えします。
全体像を把握しておくことで、「うちの厨房には何が必要なのか」が見えてきます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 動力電源工事 | 業務用オーブン、フライヤー、食洗機など、大きな電力を使用する機器のために200V電源を設置。安定した電力供給を確保します。 |
| 照明設備工事 | 調理・洗浄・保管など各エリアに適した照度の照明を配置し、作業効率と安全性を高めます。 |
| コンセント・スイッチ工事 | 小型の厨房機器や調理器具に対応する100Vコンセントや、機器操作用スイッチを設置し、使いやすい動線を確保します。 |
| 分電盤・配線工事 | 厨房全体の電気を安全に管理する分電盤を設置し、各機器に適切に電力を供給できるよう配線を行います。 |
| 換気・空調用電源工事 | 排気フード、換気扇、業務用エアコンなどの電源を整備し、快適で衛生的な厨房環境を維持します。 |
| 安全設備工事 | 漏電遮断器、アース工事、非常灯・誘導灯などを設置し、火災や感電などのリスクを防止します。 |
厨房の電気工事は、調理機器を動かすだけでなく、働く人の安全と快適さを守るための大切な役割も担っています。
たとえば、照明が暗いと食材の鮮度や調理の仕上がりを確認しにくくなりますし、換気が不十分だと熱や煙がこもって作業効率が下がってしまいます。
万が一の火災や停電に備え、非常灯や誘導灯を法令基準に沿って設置することは、安全確保上必須です。
動力電源は、業務用機器の性能を最大限に引き出すために必要なものです。
家庭用の100V電源では動かせない高出力の機器も、200Vの動力電源があればしっかり稼働します。
分電盤は、厨房全体の電気を管理し、各機器へ安全に電力を供給する重要な設備です。
ここで電力の配分を適切に行うことで、複数の機器を同時に使っても安定して電気が供給されます。
安全設備については、消防法や建築基準法で設置が義務付けられているものもあります。
開業や改装の際には、必ず専門業者と一緒に確認しておきましょう。
こうした設備を一つひとつ丁寧に整えていくことで、「機器がしっかり動く」「安全に調理できる」「快適に働ける」という、理想の厨房環境が形になっていきます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、信頼できる業者と一緒に進めれば、安心してお店をスタートできますよ。
飲食店の厨房の電気工事の動力の基礎と200Vを選ぶ理由
厨房機器のカタログを見ていると、「単相200V」「三相200V」といった言葉が出てきて、「どう違うんだろう」と戸惑ったことはありませんか。
家庭では100Vが一般的ですが、業務用の厨房機器では200Vの電源が必要になることが多くあります。
ここでは、動力電源の基本と、なぜ200Vが選ばれるのかを、わかりやすくお伝えします。
電源の仕組みを知っておくことで、機器選びや工事の相談がスムーズに進みます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 単相100V | 家庭用と同じ電源で、小型の厨房機器、照明、コンセントなどに使用。取り扱いやすく、一般的な設備に幅広く対応します。 |
| 単相200V | 中型の業務用機器(小型オーブン、卓上フライヤーなど)に使用。100Vより効率よく電力を供給でき、出力が必要な機器に適しています。 |
| 三相200V | 大型の業務用機器(業務用冷蔵庫、大型オーブン、食洗機など)に使用。高出力かつ安定した稼働が可能で、業務用厨房の主電源として採用されます。 |
| 専用回路 | 大きな電力を使用する機器ごとに、他の機器と電源を分けて安全に使用できるよう設ける回路。過負荷やトラブルを防ぎ、安全性を高めます。 |
200Vの電源が選ばれる理由は、効率と安全性にあります。
業務用の機器は、家庭用と比べて消費電力がとても大きく、100Vでは十分な電力を供給できないことがあります。
たとえば、高出力機器を100Vで動かすと電流が増加して配線が過熱するおそれがあり、安全上不適切です。
200Vにすることで、同じ電力を少ない電流で送ることができ、配線への負担が軽くなります。
また、三相200Vは、モーターを使う機器(冷蔵庫、製氷機、食洗機など)にとって理想的な電源です。
三相電源は電力の供給が安定しているため、モーターが滑らかに回り、機器の寿命も長くなります。
一方で、単相200Vは、比較的小型の機器や、三相電源の設備がない建物でも使いやすいという利点があります。
どちらを選ぶかは、機器の種類や厨房全体の電力容量によって決まります。
専用回路については、大きな電力を使う機器ごとに独立した配線を用意することで、他の機器と同時に使ってもブレーカーが落ちにくくなります。
たとえば、フライヤーと食洗機を同時に使う場合、それぞれに専用回路があれば、安心して調理を進められます。
電源の選び方は、機器のメーカー仕様書に必ず記載されています。
もし「単相と三相、どちらがいいのかわからない」と感じたら、専門業者に相談すれば、厨房の状況に合わせて最適な提案をしてもらえます。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえておくだけで、安全で効率的な厨房づくりに大きく近づけますよ。
飲食店の厨房の電気工事で知っておく法令と検査の流れ
飲食店を開業するとき、保健所や消防署の検査を受ける必要があることは、多くの方がご存じだと思います。
その中で、厨房の電気設備についても、法令に基づいた基準を満たしているかどうかが確認されます。
「電気工事って、どんなルールがあるんだろう」「検査で指摘されたらどうしよう」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ここでは、厨房の電気工事に関わる主な法令と、検査の流れをわかりやすく整理してお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電気事業法 | 電気工事は有資格者(電気工事士)による施工が義務付けられています。感電や火災事故を防止するため、安全基準に基づいた施工が求められます。 |
| 消防法 | 非常灯・誘導灯・自動火災報知設備など、火災発生時に安全に避難できる設備の設置が義務付けられています。厨房内では特に防火性能を備えた照明や配線が重要です。 |
| 建築基準法 | 建物の用途・規模に応じ、電気設備や防災設備の設置基準が定められています。厨房を含む用途変更や増築時には、法適合確認が必要となります。 |
| 食品衛生法 | 調理エリアの照度(明るさ)基準や、水回り・電気設備の衛生保持が求められます。防水・防塵仕様の照明やコンセントが推奨されます。 |
電気工事を行う際には、必ず電気工事士の資格を持つ専門業者に依頼する必要があります。
これは電気事業法および電気工事士法で定められており、無資格者による工事は法律で禁止されています。
▶︎参考【経済産業省】電気工事士法(昭和35年8月1日法律第139号)の逐条解説
適切な資格を持つ業者が施工することで、安全性が確保され、検査もスムーズに進みます。
消防法では、飲食店の規模や用途に応じて、非常灯や誘導灯の設置が義務付けられています。
これらは、万が一の火災や停電時に、お客様やスタッフが安全に避難するために欠かせない設備です。
また、自動火災報知設備についても、厨房の面積や建物の構造によって設置が必要になることがあります。
建築基準法では、建物の用途や規模に応じて、電気設備の配置や容量に関する基準が定められています。
特に、厨房のように火気を使う場所では、配線の耐熱性や防火区画への配慮が求められます。
食品衛生法では、厨房内の照明について、十分な明るさを確保することが求められています。
調理場や洗浄場では、食材の状態や汚れをしっかり確認できるよう、適切な照度が必要です。
検査の流れとしては、工事完了後に電気工事業者の自主検査を実施し、地域の保健所や消防署による現地確認を受けるのが一般的です。
このとき、非常灯や誘導灯が正しく点灯するか、配線が適切に施工されているか、照明の明るさが基準を満たしているかなどがチェックされます。
▶︎参考【厚生労働省】食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針
もし不備が見つかった場合は、再工事が必要になることもありますので、事前に専門業者としっかり打ち合わせをしておくことが大切です。
法令や検査と聞くと難しく感じるかもしれませんが、信頼できる業者と一緒に進めれば、必要な手続きを漏れなく進められます。
開業や改装をスムーズに進めるためにも、早めに相談しておくと安心ですよ。

飲食店の厨房で電気工事を進めるとき、多くの方が共通して抱える悩みがあります。
「ランチタイムやディナーのピーク時に、電気が足りなくなるのでは」「居抜き物件の配線をそのまま使っても大丈夫なのか」「保健所や消防の検査で指摘されたらどうしよう」といった不安は、誰もが一度は感じるものです。
開業準備を進めるなかで、厨房機器のカタログを見ながら「本当にこの電源で動くのかな」と心配になったり、工事業者から専門的な説明を受けても「結局、何をすればいいんだろう」と迷ったりすることもあるかもしれませんね。
すでに営業中の方でも、「最近ブレーカーがよく落ちるようになった」「新しい機器を入れたいけれど、今の電気容量で大丈夫か不安」と感じることがあるのではないでしょうか。
こうした悩みは、事前にしっかり対策を立てておくことで、多くの場合は解消できます。
ここでは、厨房の電気工事でよくある3つの悩みと、その背景について整理してお伝えします。
自分のお店に当てはまるものがないか、一緒に確認していきましょう。
どの悩みも、決して珍しいものではありません。
多くの方が同じように心配しながら、専門業者と相談しながら解決してきた道のりです。
ここで悩みの正体を知っておくことで、次にどんな対策を取ればいいのかが見えてきますし、業者さんとのやりとりもぐっとスムーズになります。
まずは「なぜその悩みが生まれるのか」「どんなリスクがあるのか」を見ていきましょう。
飲食店の厨房の電気工事でピーク時にブレーカーが落ちる悩み
ランチタイムやディナーのピーク時に、オーブンとフライヤーを同時に使った瞬間、ブレーカーが落ちてしまった経験はありませんか。
お客様をお待たせしてしまうだけでなく、調理がストップして、せっかくの料理が台無しになってしまうこともあります。
「なぜ、こんなことが起きるんだろう」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ピーク時にブレーカーが落ちてしまう原因と、その背景を整理してお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電気容量の不足 | 厨房全体で使える電力の上限を超えて、複数の機器を同時に使ってしまうと、ブレーカーが作動します。 |
| 専用回路の不足 | 大きな電力を使う機器ごとに専用の回路がないと、他の機器と電源を共有してしまい、負担が集中します。 |
| 同時使用率の見積もり不足 | 開業時に「これくらいなら大丈夫だろう」と考えていた使い方が、実際の営業では超えてしまうことがあります。 |
| 古い配線や分電盤 | 居抜き物件では配線や分電盤が現行機器の消費電力に適合しない場合があるため、事前に電気容量と配線の確認が必要です。 |
ブレーカーが落ちる理由は、簡単に言えば「使いたい電力が、供給できる電力を超えてしまった」ことにあります。
たとえば、厨房全体で30アンペアの契約をしているとき、オーブンで15アンペア、フライヤーで10アンペア、食洗機で10アンペアを同時に使おうとすると、合計で35アンペアになり、容量をオーバーしてしまいます。
ブレーカーは、こうした過負荷から配線や機器を守るために、自動的に電気を遮断する仕組みです。
専用回路がないことも、大きな原因の一つです。
大型の業務用機器は、それぞれに専用の回路を用意することで、他の機器と電源を分けて使えるようになります。
専用回路がないと、複数の機器が同じ回路を共有することになり、負担が一つの回路に集中してしまいます。
また、開業時に計画した電気容量が、実際の営業では足りなくなることもよくあります。
たとえば、「オーブンとフライヤーを同時に使うことは少ないだろう」と考えていても、ピーク時には想定以上に機器を同時稼働させることがあります。
こうした同時使用率の見積もりが甘いと、後から電気容量不足に気づくことになります。
さらに、居抜き物件では配線や分電盤が現行機器の消費電力に適合しない場合があるため、事前に電気容量と配線の確認が必要です。
前のお店の業態が違えば、使う機器も電力も異なりますので、配線や分電盤の見直しが必要になることがあります。
ブレーカーが落ちる問題は、飲食店業界団体の事例集で、開業後や機器更新時に多数報告されています。
ブレーカーが落ちてしまう問題は電気容量の見直しや専用回路の増設、分電盤の交換といった対策を取ることで、ピーク時でも安心して調理できる環境を整えることができますよ。
飲食店の厨房の電気工事で前の店の配線をそのまま使う不安
居抜き物件を引き継ぐとき、「前のお店の配線をそのまま使っても大丈夫なのかな」と不安に感じたことはありませんか。
厨房機器がすでに設置されていて、配線も整っているように見えると、「このまま使えば工事費も抑えられるし、便利かも」と思うかもしれません。
でも、実際に営業を始めてから「思っていたのと違った」と気づくこともあります。
ここでは、前のお店の配線をそのまま使うことに潜むリスクと、注意すべきポイントを整理してお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 業態の違い | 前のお店と業態が異なると、使う機器の種類や消費電力が大きく変わり、配線が対応できないことがあります。 |
| 配線の劣化 | 長年使われてきた配線は、見た目ではわからない劣化が進んでいることがあり、漏電や過熱のリスクが潜んでいます。 |
| 専用回路の不足 | 新しく導入する機器に対して、専用回路が用意されていない場合、ブレーカーが落ちやすくなります。 |
| 安全基準の変化 | 法令や安全基準は年々更新されており、古い配線では現在の基準を満たしていないこともあります。 |
前のお店と業態が異なると、使う機器の種類や消費電力が大きく変わり、配線が対応できないことがあります。
たとえば、業態変更により高出力機器が必要になる場合があり、その際には電源容量や配線の変更が必要になることがあります。
カフェから焼肉店へ業態を変えるケースでは、排気フードやグリルといった高出力の機器を新たに導入することになり、前のお店の配線や電源容量では対応しきれないことがあります。
配線の劣化も、見落としがちなリスクです。
配線は長年使われるうちに、被覆が傷んだり、内部の銅線が酸化したりして、性能が低下していきます。
見た目には問題がなくても、漏電や過熱のリスクが潜んでいることがあります。
特に厨房は、水や油、熱にさらされる環境ですので、配線へのダメージが大きくなりやすい場所です。
専用回路については、前のお店で使っていた機器と、あなたが新しく導入する機器が同じとは限りません。
居抜き物件では新規導入機器用の専用回路が不足している場合があり、追加工事が必要なことがあります。
大型のフライヤーや食洗機を新たに導入する場合、専用の回路が必要になることが多いのですが、その回路が用意されていないこともあります。
また、法令や安全基準は定期的に更新されています。
前のお店が営業していた当時は問題なかった配線でも、現在の基準では不十分とされることがあります。
特に、アース工事や漏電遮断器の設置といった安全対策は、近年重視されるようになっています。
居抜き物件を引き継ぐときは、まず専門業者に配線の状態を点検してもらうことをおすすめします。
前のお店の配線設備が現行の業態や機器の消費電力に適合しない場合があるため、事前点検が必要です。
点検の結果、配線の一部を交換したり、専用回路を追加したりする必要があるかもしれません。
それは開業後のトラブルを防ぎ、安全に長く営業を続けるための大切な投資です。
最初にしっかり確認しておくことで、安心してお店をスタートできますよ。
飲食店の厨房の電気工事で検査前に指摘が出る心配
「保健所や消防の検査で指摘が出たらどうしよう」という不安は、開業準備中の方だけでなく、すでに営業中の方も感じることがあるのではないでしょうか。
改装や機器の入れ替えを検討しているとき、定期的な立入検査が近づいているとき、「電気設備で何か不備があるかもしれない」と心配になることもあるかもしれません。
検査で指摘を受けると、営業に支障が出たり、再工事が必要になったりすることもあります。
ここでは、検査でよく指摘される電気設備のポイントを整理してお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 非常灯・誘導灯の不備 | 火災や停電時の避難誘導のために必要で、設置場所や明るさが基準を満たしているか確認されます。 |
| 漏電遮断器の未設置 | 漏電による感電や火災を防ぐための装置で、厨房では特に重視されます。 |
| アース工事の不足 | 金属製の厨房機器には、感電防止のためのアース工事が必要です。 |
| 照明の照度不足 | 調理場や洗浄場では、食材の状態を確認できる十分な明るさが求められます。 |
| 防水コンセントの未使用 | 水気の多い厨房では、防水仕様のコンセントを使用することが求められます。 |
非常灯や誘導灯は、消防法に基づいて設置が義務付けられています。
設置場所や照度が基準を満たしていない場合、また経年劣化で点灯しない場合にも、検査で指摘を受けます。
漏電遮断器は、漏電による感電や火災を防ぐ重要な安全装置です。
厨房は水気が多く漏電リスクが高いため、設置は特に重視されます。
アース工事は、金属製の厨房機器に施す感電防止の工事です。
冷蔵庫、オーブン、食洗機などの金属部分から、万が一の漏電時に電気を地面に逃がします。
アース線が正しく接続されているかは、検査でよく確認される項目です。
照明の照度については、食品衛生法に基づく基準があります。
調理場や洗浄場では、食材の鮮度や汚れをしっかり確認できる明るさが必要です。
防水コンセントは、水気の多い厨房で安全に電気を使うために必要です。
シンク周辺や洗浄エリアでは、防水仕様のコンセントが推奨されています。
検査で指摘を受けないためには、専門業者と事前に確認しておくことが大切です。
開業時はもちろん、改装や機器入れ替えの際にも、法令や基準を満たしているか点検してもらいましょう。
定期点検を受けている店舗でも、経年劣化で不備が生じることがありますので、日頃から設備の状態を確認しておくと安心です。

厨房の電気工事でよくある悩みを見てきましたが、「では、どうすればいいのか」が気になるところですよね。
ブレーカーが落ちない設計、安全に長く使える配線、検査をスムーズに通過できる設備。
これらを実現するためには、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、厨房の電気工事を進めるときに知っておきたい選び方と対策を、具体的にお伝えします。
「容量計算ってどうやるの」「単相と三相、どう選べばいいの」「安全対策って何をすればいいの」といった疑問が浮かぶこともあるかもしれませんね。
基本を知っておくことで、工事業者との打ち合わせがスムーズになりますし、納得して理想の店舗づくりを進めることができます。
開業準備中の方も、改装や機器の入れ替えを考えている方も、ここで紹介する対策を参考にしていただければと思います。
安全で快適な厨房をつくるための第一歩を、一緒に踏み出していきましょう。
飲食店の厨房の電気工事は容量計算と専用回路で”落ちない”設計に
ピーク時にブレーカーが落ちない厨房をつくるには、「容量計算」と「専用回路」がカギになります。
この2つを押さえることで、複数の機器を同時に使っても安定して電気が供給され、調理がスムーズに進みます。
ここでは、容量計算と専用回路について、わかりやすくお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 容量計算 | 厨房全体で使う機器の消費電力を合計し、同時に使う割合を考えて必要な電力容量を算出します。 |
| 同時使用率 | すべての機器を同時に使うわけではないため、実際の使用パターンを想定して計算します。 |
| 専用回路 | 大きな電力を使う機器ごとに独立した回路を設け、他の機器と電源を分けます。 |
| 予備回路 | 将来の機器増設に備えて、分電盤に余裕をもたせた回路を確保しておきます。 |
容量計算は、厨房で使う機器の消費電力を合計して、必要な電力容量を算出する作業です。
たとえば、オーブン3kW、フライヤー5kW、食洗機4kWなら、単純合計で12kWになります。
ただし、すべての機器を同時にフル稼働させるとは限らないため、同時使用率を考慮して計算します。
同時使用率は、厨房の営業スタイルや調理の流れによって異なります。
ピーク時に複数機器を同時使用するお店では高めに、タイミングをずらせるお店では低めに設定できます。
この見積もりが甘いと後から容量不足に悩むことになるため、余裕をもった設定が大切です。
専用回路は、大きな電力を使う機器ごとに独立した配線を用意することです。
オーブン、フライヤー、食洗機、大型冷蔵庫には、それぞれ専用の回路を設けることで、他の機器と電源を共有せずに済みます。
予備回路は、将来の機器増設に備えて分電盤に余裕をもたせておく考え方です。
後から機器を追加したくなったとき、予備回路があれば大掛かりな工事をせずに対応できます。
厨房の容量設計や回路設計は、資格を持つ電気工事業者が機器の仕様や使用状況を踏まえて行うのが原則です。
「このくらいの機器を、こんなふうに使いたい」という希望を伝えることで、最適な設計を考えてもらえます。
では、実際に単相と三相の電源をどう選ぶのか、そして分電盤や回路設計をどう考えればいいのか、次で詳しく見ていきましょう。
厨房機器のカタログを見ると、「単相200V」「三相200V」といった表記が出てきて、どちらを選べばいいのか迷うことがあるかもしれません。
実は、単相と三相にはそれぞれ特徴があり、機器の種類や厨房の電源環境によって使い分けることが大切です。
ここでは、単相と三相の違いと、選び方のポイントをわかりやすくお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 単相200V | 比較的小型の機器に使われ、多くの建物で利用できる電源。 |
| 三相200V | 大型機器やモーター駆動の機器に適しており、効率よく安定した電力供給が可能。 |
| 機器の仕様 | メーカーの仕様書に必要な電源の種類が記載されているため、必ず確認が必要。 |
| 建物の受電設備 | 建物によっては三相電源が引き込まれていない場合があり、新たに引き込み工事が必要になることも。 |
単相200Vは、比較的小型の業務用機器に使われることが多く、卓上フライヤーや小型オーブンなどが該当します。
多くの建物で利用できる電源のため、導入しやすいという利点があります。
三相200Vは、大型の業務用機器やモーター駆動の機器に適しています。
業務用冷蔵庫、大型オーブン、食洗機、製氷機などは、三相電源を使うことで効率よく安定した稼働が可能になります。
三相電源はモーターの回転が滑らかになり、負荷変動が少なくなるため機器への負担が軽減されます。
機器の仕様については、メーカーのカタログや仕様書に必ず記載されていますので、購入前に確認しておきましょう。
「単相専用」と書かれている機器に三相電源を接続することはできませんし、その逆も同様です。
建物の受電設備も重要なポイントです。
三相電源が建物に引き込まれていない場合、新たに引き込み工事が必要になることがあります。
居抜き物件では前店舗の電源設備が残っている場合があり、新業態に適合するか事前確認が必要です。
単相と三相のどちらを選ぶかは、導入したい機器の仕様と建物の電源環境によって決まります。
専門業者に相談すれば、機器リストをもとに最適な電源構成や、単相と三相を組み合わせた設計も提案してもらえます。
不安や質問がある場合は、遠慮せず専門業者に相談してみてください。
分電盤と回路設計は、厨房全体の電気を管理する大切な仕組みです。
「分電盤って何をするもの?」「回路設計ってどう考えればいいの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ここでは、分電盤の役割と回路設計の基本的な考え方を、わかりやすくお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 分電盤 | 厨房全体の電気を管理し、各機器へ安全に電力を供給する設備。 |
| 主幹ブレーカー | 建物全体の電気を制御し、過負荷時に自動で遮断する装置。 |
| 分岐ブレーカー | 各回路ごとに設置され、個別の機器や照明を保護する装置。 |
| 漏電遮断器 | 漏電を検知して自動で電気を遮断し、感電や火災を防ぐ装置。 |
| 回路の分け方 | 機器の種類や消費電力に応じて、適切に回路を分けて配線する。 |
分電盤は、厨房全体の電気を管理し、各機器へ安全に電力を供給する設備です。
建物に引き込まれた電気を受け取り、厨房内の各機器や照明に適切に分配する役割を担っています。
主幹ブレーカーは、建物全体の電気を制御する装置です。
厨房全体で使える電力の上限を管理し、過負荷になると自動的に電気を遮断して、配線や機器を守ります。
分岐ブレーカーは、各回路ごとに設置され、個別の機器や照明を保護します。
たとえば、オーブン専用の回路、フライヤー専用の回路、照明用の回路というように、それぞれに分岐ブレーカーが設けられます。
一つの回路で問題が起きても、他の回路には影響が出ないようにする仕組みです。
漏電遮断器は、漏電を検知して自動で電気を遮断し、感電や火災を防ぐ装置です。
厨房は水気が多く漏電のリスクが高いため、漏電遮断器の設置は特に重要です。
回路の分け方については、機器の種類や消費電力に応じて適切に設計する必要があります。
大型の業務用機器には専用回路を設け、照明やコンセントは別の回路にまとめるといった配分を行います。
回路を適切に分けることで、ブレーカーが落ちにくくなり、メンテナンスもしやすくなります。
分電盤や回路設計については、専門業者が厨房の規模や機器構成をもとに最適な設計を提案してもらえます。
「どのくらいの容量が必要か」「予備回路はどれくらい確保すればいいか」といった疑問がある場合は、遠慮せず専門業者に相談してみてください。
飲食店の厨房の電気工事は防水・アース・漏電保護で安全性を高めよう
厨房は水や油、熱にさらされる環境のため、電気設備の安全対策は特に重要です。
防水対策、アース工事、漏電保護の3つをしっかり行うことで、感電や火災のリスクを大きく減らすことができます。
ここでは、これらの安全対策について、わかりやすくお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 防水コンセント | 水気の多い場所で使用するための、水の浸入を防ぐ仕様のコンセント。 |
| アース工事 | 金属製の機器に施す工事で、漏電時に電気を地面に逃がして感電を防ぐ。 |
| 漏電遮断器 | 漏電を検知して自動的に電気を遮断し、感電や火災を防ぐ装置。 |
| 配線の保護 | 水や油、熱から配線を守るための保護管や防水加工。 |
防水コンセントは、水気の多い厨房で安全に電気を使うために必要です。
シンク周辺や洗浄エリアでは、通常のコンセントでは水がかかったときに漏電や感電のリスクが高まります。
防水仕様のコンセントを使用することで、安全性が大きく向上します。
アース工事は、金属製の厨房機器に施す感電防止の工事です。
冷蔵庫、オーブン、食洗機などの金属部分に触れたとき、万が一漏電していても電気を地面に逃がすことで感電を防ぎます。
保健所や消防の検査では、金属製機器のアース線接続状態を確認する場合があります。
漏電遮断器は、漏電を検知して自動的に電気を遮断し、感電や火災を防ぐ装置です。
厨房は水を使う場面が多く、配線や機器が濡れるリスクが高いため、漏電遮断器の設置は特に重要です。
分電盤に漏電遮断器が組み込まれているか、事前に確認しておくことが大切です。
配線の保護については、水や油、熱から配線を守るための対策が必要です。
厨房では配線が床や壁に這わせられることも多く、調理中の水しぶきや油、高温の機器からの熱にさらされます。
保護管を使ったり、防水加工を施したりすることで、配線の劣化を防ぎ、長く安全に使える環境を整えられます。
開業前や定期点検の際に、以下を確認しておくと安心です。
- 防水コンセント: シンク周辺や洗浄エリアに防水仕様のコンセントが設置されているか。
- アース接続: 冷蔵庫、オーブン、食洗機などの金属製機器にアース線が正しく接続されているか。
- 漏電遮断器: 分電盤に漏電遮断器が組み込まれており、テストボタンで正常に作動するか。
- 配線の保護: 配線に保護管が使われているか、または防水加工が施されているか。
- 破損の有無: 防水コンセントやアース線に破損や劣化が見られないか。
こうした安全対策は、開業時だけでなく、日頃の点検でも大切にしたいポイントです。
確認を習慣にしておくことで、長く安心して営業を続けられます。
飲食店の厨房の電気工事はLED・換気・空調で省エネを進めよう
電気代の負担は、飲食店の経営にとって大きな課題の一つです。
厨房では多くの機器が長時間稼働するため、電力消費量も多くなりがちです。
LED照明への切り替えや、高効率の換気・空調設備の導入によって、電気代を抑えながら快適な厨房環境を保つことができます。
ここでは、省エネにつながる電気工事のポイントをお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| LED照明 | 従来の照明と比べて消費電力が少なく、長寿命で交換の手間も減らせる。 |
| 高効率換気設備 | 排気フードや換気扇を高効率タイプにすることで、電力消費を抑えられる。 |
| 業務用エアコン | 省エネ性能の高い機種を選ぶことで、空調にかかる電気代を削減できる。 |
| タイマー・センサー | 人感センサーやタイマーを活用して、不要な時間帯の電力消費を抑える。 |
LED照明は、従来の蛍光灯や白熱灯と比べて消費電力が大幅に少なく、長寿命という特徴があります。
厨房の照明をLEDに切り替えることで、電気代を削減できるだけでなく、電球交換の頻度も減らせます。
調理エリアや洗浄エリアでは十分な明るさが必要ですが、LED照明なら省エネと明るさを両立できます。
高効率換気設備は、排気フードや換気扇を省エネ性能の高いタイプにすることで、電力消費を抑えられます。
厨房では常に換気設備が稼働しているため、ここでの省エネ効果は大きくなります。
特に、インバーター制御を搭載した換気設備は、必要な風量に応じて自動調整するため、無駄な電力を使わずに済みます。
業務用エアコンについても、省エネ性能の高い機種を選ぶことで、空調にかかる電気代を削減できます。
厨房は調理による熱が発生しやすく、空調の負担が大きい場所です。
最新の省エネ型エアコンは、効率よく温度管理ができるため、快適な環境を保ちながら電気代を抑えられます。
タイマーやセンサーの活用も、省エネには効果的です。
人感センサーを使えば、人がいないときに自動で照明を消すことができます。
また、営業時間外にタイマーで換気や空調を自動停止させることで、無駄な電力消費を防げます。
省エネ設備への切り替えは、初期費用がかかることもありますが、長期的に見れば電気代の削減につながります。
自治体によっては、LED化や省エネ機器導入に対する補助金制度が用意されている場合もありますので、活用を検討してみるのも良いでしょう。
日々の電気代を抑えながら、快適な厨房環境をつくることで、長く安心して営業を続けるきっかけとなることでしょう。

ここまで、厨房の電気工事の基本や選び方、安全対策、省エネ対策について見てきました。
「実際にどんな流れで工事が進むんだろう」「完成した後はどうやって管理すればいいのか」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、電気工事の現場で実際にどんなことが行われるのか、そして完成後の点検や緊急時の備えについて、わかりやすくお伝えします。
工事の段取りを知っておくことで、開業や改装のスケジュールが立てやすくなりますし、業者とのやりとりもスムーズになります。
また、日頃の点検や緊急時の対応を知っておくことで、長く安心して厨房を使い続けることができます。
新しくお店を開く方も、すでに営業中で設備の見直しを考えている方も、現場のイメージを持っておくことで、次の一歩が踏み出しやすくなります。
それでは、工事の流れから点検、そして緊急時の備えまで、一緒に確認していきましょう。
飲食店の厨房の電気工事の段取りと工程の流れ
電気工事は、計画から完成まで、いくつかの段階を経て進められます。
「どんな順番で工事が進むんだろう」「どのくらいの期間がかかるのか」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ここでは、厨房の電気工事の段取りと、工程の流れをわかりやすくお伝えします。
全体の流れを把握しておくことで、スケジュールが立てやすくなります。
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 現地調査 | 既存の配線や分電盤、電力容量を確認し、厨房の状況を把握する。 |
| 機器リスト作成 | 導入する厨房機器の種類、消費電力、設置場所を整理する。 |
| 容量計算・設計 | 必要な電力容量を算出し、専用回路や分電盤の設計を行う。 |
| 見積もり・工程表 | 工事内容と費用、完成までのスケジュールを提示する。 |
| 配線・機器設置工事 | 分電盤の設置、配線工事、機器への電源接続を行う。 |
| 検査・引き渡し | 電気の通電確認、安全検査を行い、問題がなければ引き渡す。 |
現地調査では、既存の配線や分電盤の状態、建物への電力引き込み容量などを確認します。
居抜き物件では既存配線が使用可能か事前に確認する必要があります。
この段階で、厨房のレイアウトや給排水・ガス配管との位置関係も確認しておくことが大切です。
機器リスト作成では、導入する厨房機器の種類、消費電力、設置場所を整理します。
オーブン、フライヤー、食洗機、冷蔵庫など、それぞれの機器がどの電源を必要とするのかを明確にします。
メーカーのカタログや仕様書をもとに、正確な情報を集めておくとスムーズです。
容量計算・設計では、機器リストをもとに必要な電力容量を算出し、専用回路や分電盤の設計を行います。
同時使用率を考慮しながら、ピーク時でもブレーカーが落ちない設計を目指します。
見積もりと工程表が提示されたら、工事内容、費用、完成までのスケジュールを確認しましょう。
他の内装工事との調整も必要になるため、全体のスケジュールを考慮して進めます。
配線・機器設置工事では、分電盤の設置、配線工事、機器への電源接続を行います。
壁や床に配線を通し、各機器に専用回路を接続していきます。
この段階で、アース工事や漏電遮断器の設置も行われます。
検査・引き渡しでは、電気の通電確認や安全検査を行います。
漏電遮断器が正常に作動するか、アース線が正しく接続されているかなどを確認します。
問題がなければ引き渡しとなります。
厨房電気工事期間は、規模によって1〜2週間から2〜3ヶ月程度かかる場合があります。
開業や改装の日程に合わせて、余裕をもったスケジュールを組んでおくと安心です。
飲食店の厨房の電気工事の点検と予防保全の進め方
気設備は、工事が完成したら終わりではなく、日頃の点検と予防保全が大切です。
「いつ、何を確認すればいいんだろう」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ここでは、厨房の電気設備の点検と、予防保全の進め方をわかりやすくお伝えします。
定期的な点検を習慣にすることで、トラブルを未然に防ぎ、長く安心して営業を続けられます。
| 点検の種類 | 内容 |
|---|---|
| 日常点検 | 営業前後に目視で配線の損傷やコンセントの異常がないか確認する。 |
| 月次点検 | 漏電遮断器のテストボタンを押して正常に作動するか確認する。 |
| 年次点検 | 専門業者による配線、分電盤、アース接続の総合的な点検を受ける。 |
| 臨時点検 | 機器の入れ替えや異常を感じたときに、随時点検を行う。 |
日常点検は、営業前後に目視で行う簡単なチェックです。
配線に傷や破損がないか、コンセントに焦げ跡や変色がないか、機器から異常な音や臭いがしないかを確認します。
特に、水気の多いシンク周辺や洗浄エリアでは、配線が濡れていないか注意して見ておきましょう。
月次点検では、漏電遮断器のテストボタンを押して正常に作動するかを確認します。
テストボタンを押すと、正常な場合はブレーカーが落ちて電気が遮断されます。
その後、ブレーカーを上げれば元に戻ります。
もしテストボタンを押してもブレーカーが落ちない場合は、漏電遮断器が故障している可能性がありますので、早めに点検を依頼しましょう。
年次点検は、専門業者による総合的な点検です。
配線の劣化状態、分電盤の接続部分、アース線の接続状態など、目視だけではわからない部分まで確認してもらえます。
法令によって定期点検が義務付けられている設備もありますので、年に一度は専門業者に点検を依頼することをおすすめします。
臨時点検は、機器の入れ替えや異常を感じたときに行う点検です。
新しい機器を導入したときや、「最近ブレーカーがよく落ちる」「配線から焦げ臭いにおいがする」といった異常に気づいたときは、すぐに点検を依頼しましょう。
毎日
- 配線に傷や破損がないか
- コンセントに焦げ跡や変色がないか
- 機器から異常な音や臭いがしないか
- シンク周辺の配線が濡れていないか
毎月
- 漏電遮断器のテストボタンで正常に作動するか
- 防水コンセントに破損がないか
年次
- 専門業者による配線・分電盤の総合点検を受けたか
- アース線の接続状態を確認してもらったか
緊急時(異常時)
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 配線から焦げ臭いにおいがする
予防保全は、故障やトラブルが起きる前に対策を取ることです。
たとえば、配線の被覆が劣化している箇所を早めに交換したり、古いブレーカーを新しいものに更新したりすることで、突然の故障を防げます。
点検で指摘された箇所は、後回しにせず早めに対応しておくことが大切です。
定期的な点検と予防保全を続けることで、厨房の電気設備を長く安全に使い続けることができます。
日頃から設備の状態に気を配り、異常を感じたら早めに対処する習慣をつけておくことをおすすめします。
飲食店の厨房の電気工事の緊急対応と”止めない厨房”の備え
営業中に突然電気のトラブルが起きたら、調理が止まってしまい、お客様にご迷惑をかけてしまいます。
「もし夜中に冷蔵庫が止まったら」「ピーク時にブレーカーが落ちたら」と考えると、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、緊急時の対応と、トラブルを最小限に抑えるための備えについてお伝えします。
事前に準備をしておくことで、万が一のときも落ち着いて対処できます。
| 備えの内容 | 説明 |
|---|---|
| 緊急連絡先の確認 | 電気工事業者の連絡先を見やすい場所に掲示しておく。 |
| 予備回路の確保 | 将来の機器増設や緊急時の切り替えに備えて、予備回路を設けておく。 |
| 応急処置の知識 | ブレーカーが落ちたときの復旧手順を、スタッフ全員で共有しておく。 |
| 定期点検の実施 | トラブルを未然に防ぐため、定期的な点検を欠かさない。 |
緊急連絡先の確認は、トラブルが起きたときに最初に必要な情報です。
電気工事業者の連絡先を、厨房の見やすい場所に掲示しておきましょう。
深夜・早朝にも対応できる電気工事業者を事前に把握しておくと安心です。
予備回路の確保は、緊急時の切り替えや、将来の機器増設に役立ちます。
分電盤に余裕をもたせて予備回路を設けておくことで、一つの回路にトラブルが起きても、他の回路で営業を続けられることがあります。
応急処置の知識は、スタッフ全員で共有しておくことが大切です。
たとえば、ブレーカーが落ちたときは、まず使用中の機器の電源を切ってから、ブレーカーを上げるという手順を覚えておきましょう。
何度もブレーカーが落ちる場合は、無理に復旧させようとせず、電気工事業者に連絡してください。
定期点検の実施は、トラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法です。
配線の劣化や機器の不具合を早期に発見できれば、営業中の突然のトラブルを避けられます。
また、冷蔵庫や冷凍庫には、温度異常を知らせるアラーム機能がついている機種もあります。
こうした機能を活用することで、夜間や休業日の異常にも気づきやすくなります。
“止めない厨房”をつくるためには、日頃の備えが何より大切です。
定期点検を習慣にし、緊急時の連絡先や応急処置の手順を確認しておくことで、万が一のときも慌てずに対応できます。
トラブルを完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、被害を最小限に抑える準備は今からでもできます。
安心して営業を続けるために、できることから始めてみてくださいね。

飲食店の厨房における電気工事は、単なる作業ではなく、安全で安定した厨房運営を支える大切な基盤です。新たに開業する飲食店や、既存店を改装する際、適切な電気工事が行われていないと、厨房機器が正常に動作しない、または安全上のリスクが高まる原因となることがあります。
特に、厨房機器は高出力のものが多いため、動力の選定や専用回路の設計が不可欠です。食洗機やフライヤー、業務用オーブンなどの機器を同時に使う際、電力容量が足りていないと、ブレーカーが落ちたり、機器が正常に動作しなくなることもあります。こうした問題を未然に防ぐためには、事前に適切な容量計算を行い、必要な回路設計をすることが重要です。
また、法令や基準を遵守することも大切です。保健所や消防法に基づく確認や工事がきちんと行われていないと、営業許可が降りないこともあります。 防水コンセント、アース、漏電防止措置などの設備が不足している場合、事前に指摘され、再工事が必要になることもあります。これらを防ぐためには、経験豊富な専門業者による事前の設計と施工が不可欠です。
厨房という特殊な環境では、温度や湿気、油煙が多く、電気機器が大きな負荷を受けます。だからこそ、信頼できる業者にしっかりと任せることが、長期的な安心につながります。専門業者選びはとても重要です。 多くの専門業者が親身になってサポートしてくれるでしょうが、あなたの店舗に最適な業者を選ぶことが、無駄なトラブルを防ぎ、安心して運営を続けるためのカギとなります。
林田電気工業は、半世紀以上地域の皆様と共に歩み、確かな技術と誠実な対応で多くの飲食店様の厨房電気工事を支えてきました。地域密着型のサービスを大切にし、開業から運営まで、厨房の電気工事に関するあらゆる不安をしっかりサポートいたします。
あなたの店舗にぴったりの工事を、専門知識と経験をもってお手伝いします。
半世紀の歴史!
福岡県行橋市の電気会社
林田電気工業
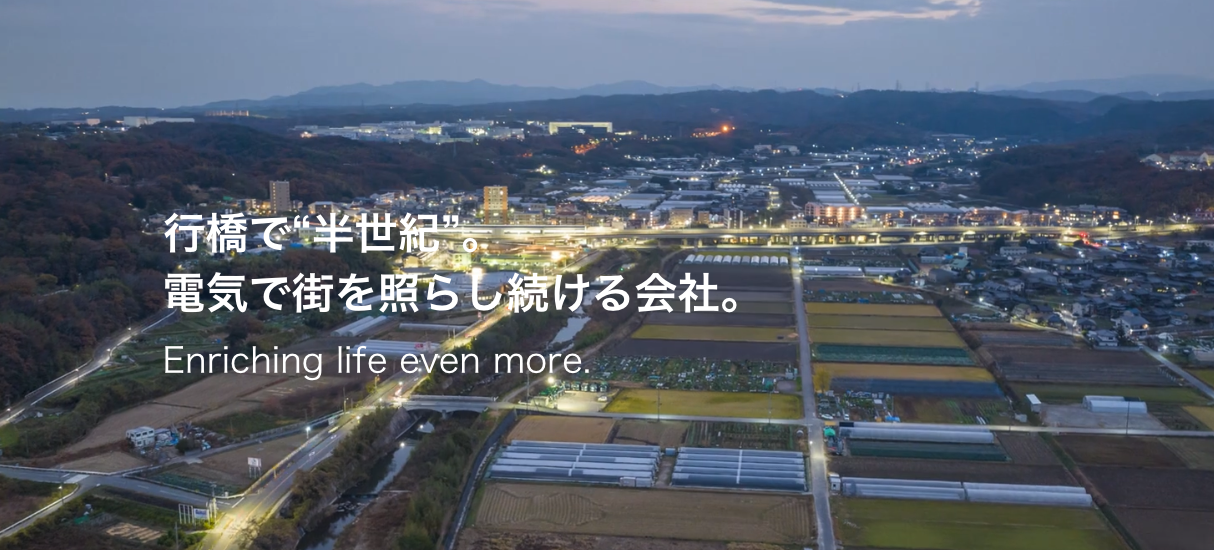
電気に関するお悩みは
お気軽にご相談ください
専任のスタッフがお客様のご不明な点にお答えいたします。お困りでしたらお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
 電気工事メディア
電気工事メディア

